 お悩み
お悩み親が高齢になり通院頻度が増えたけど、付き添いが地味にしんどい……



実家と近距離に住んでいるからといって、兄弟姉妹の中でも自分だけが付き添いをさせられている
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、高齢になった親の病院に付き添いが必要な理由や付き添いの負担を減らすコツを紹介していきます。
- 高齢になった親の病院に付き添いが必要な理由
- 高齢になった親の病院付き添いに疲れてしまう原因
- 高齢になった親の病院付き添いの負担を軽減する方法
高齢の親が病院に通うようになると「付き添いが必要か」「どこまでサポートすればよいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
特に、親が遠方に住んでいたり、仕事や育児と両立している場合、通院のたびに疲弊してしまうことも少なくありません。
本記事では、高齢の親の病院付き添いが必要な理由や、少しでも負担を軽減する方法について解説します。
高齢になった親の病院に付き添いが必要な理由
高齢になってくると身体も衰え、通院の頻度も上がります。
一方で、1人で病院に行くことが難しい場合や医師の話を聞くことが難しい場合には、家族が付き添いをしなければならないこともあるでしょう。
- 高齢者の移動手段は限られる
- 高齢者は診察内容・医師の指示を正確に理解できない恐れがある
- 高齢者は 薬の服用方法を理解できない恐れがある
それぞれ詳しく解説していきます。
高齢者の移動手段は限られる
高齢になると、免許を返納する方も増えるため、病院へは公共交通機関や徒歩で行くことになります。
しかし、高齢者の中には、体力や筋力の低下、関節の痛み、視力の衰えなどにより、公共交通機関の利用が難しくなる方もいます。
タクシーを使えば、ドアtoドアで病院まで行くことができますが、乗り降りの不便さや費用を負担に感じてしまう方もいるでしょう。
また、大学病院や総合病院などは建物の構造が必要であり、受付から診察室、会計までの移動や手続きを難しく感じる方もいるはずです。
信頼できる家族が付き添いサポートすることで、病院までの移動や病院内の移動も安心してこなせるでしょう。



大学病院などの初診では、紹介状が必要なこともあり、高齢者1人では難しく感じてしまいます
高齢者は診察内容・医師の指示を正確に理解できない恐れがある
病院では、診察や検査結果について医師から専門的な説明を受けることになります。
しかし、高齢者の中には耳が遠くなっていたり、認知機能が低下していたりして、医師の話を十分に理解できないケースもあります。
高齢者の中には「お医者さん=偉い人」と考えている方も多く、診察中は緊張してしまう方もいるのでご注意ください。



家族が付き添えば、医師の説明を一緒に聞いてメモを取ったり、不明点を代わりに質問したりできるはずです
高齢者は薬の服用方法を理解できない恐れがある
高齢になると、複数の持病を抱え、様々な薬を服用している方も多くなります。
薬の種類が増えるほど、服用のタイミングや回数、食前・食後の区別などが複雑になり、誤って服用してしまうリスクも高まります。
病院付き添いの際に家族が同行することで、薬剤師の説明を代わりにしっかり聞いたり、薬の管理方法について相談したりすることも可能です。
高齢になった親の病院付き添いに疲れてしまう6つの原因
高齢になった親の病院に付き添いが必要なことは理解しているものの、実際問題、難しかったり付き添いに疲れてしまったりするケースもあるでしょう。
- 仕事の調整が必要となる
- 病院の待ち時間が長い
- 病院が遠方にあり時間と交通費がかかる
- 他の子供たちが付き添いをしてくれず不公平感がある
- 親の病気・ケガに対して不安な気持ちになる
- 病院付き添いを負担に感じることに罪悪感を持つ
それぞれ詳しく解説していきます。
仕事の調整が必要となる
多くの病院は平日日中に受診することが多く、子供世代が付き添いをするとなると、仕事を休んだり、早退・遅刻したりしなければならないこともあるでしょう。
病院への付き添いが定期的なものとなると、有給も減ってしまいますし、休みにくいと感じてしまうこともあるはずです。
また、フリーランスやパート・アルバイトの方も時間の融通がききやすいと思われがちですが、付き添いで仕事を休むと収入源に直結するため、経済的な負担となることも多々あります。
病院の待ち時間が長い
大学病院や総合病院などは予約をしていても混雑しており、1〜2時間待たされることも珍しくありません。



急患が来た日なんかは、付き添いが1日仕事になりますよね……
親を気遣いながら、自分自身も待ち続けるという状況は、心身ともに消耗するはずです。
さらに、待合室ではWi-fiがなくスマホやPCを使い辛かったり、周囲に配慮して静かに過ごさなければならなかったりと、自由な時間のようでいて「何もできない時間」になりがちです。



この「何も進まない感じ」が、付き添いを重荷に感じさせる要因になります……
病院が遠方にあり時間と交通費がかかる
親が地方や郊外に住んでいる場合、病院までの移動だけでも大きな負担となります。
自宅と実家、病院が離れている場合には、親を実家まで迎えに行って、病院に連れていき、薬局に寄り、親を送り……と1日中運転手をさせられている気分になります。
付き添いの頻度が増すと交通費やガソリン代、駐車場代もかさみ、経済的な負担となるでしょう。



病院の駐車場って混んでいることも多く、送迎をするだけでも結構疲れますよね……
他の子供たちが付き添いをしてくれず不公平感がある
兄弟姉妹がいる場合でも「気付けば自分だけがいつも付き添っている」という状況はよくあります。
親と近くに住んでいたり、フリーな時間が取りやすかったりすることが理由で、なんとなく「お願いしやすい」存在になってしまっているのかもしれません。
最初は納得していたとしても、他の兄弟姉妹が一切手を貸さなかったり、無関心だったりすると、不公平感や孤独感がつのってくるのも無理ありません。



「なぜ私ばかりが……」と思ってしまうと、付き添いが負担となり精神的な疲れにつながってしまうでしょう
親の病気・ケガに対して不安な気持ちになる
病院に付き添うことで、親の老いや病気、ケガと向き合うこととなり、不安な気持ちになる方もいるでしょう。
診察結果や検査数値の内容によっては、将来の介護や入院、命にかかわる問題への不安がよぎることもあるからです。
特に、認知症の兆候を指摘された場合や、重い病気の診断を受けた際には、現実を受け入れるのにも時間がかかりますし「何をしてあげればいいんだろう」と漠然とした不安が湧き上がるはずです。



このような心の負荷が、付き添いという行為自体を「しんどいもの」に感じさせてしまうのです
病院付き添いを負担に感じることに罪悪感を持つ
最後に、これまで紹介してきた様々な理由により付き添いを負担に感じてしまうこと、それ自体に罪悪感を持ってしまうことも珍しくありません。



「親の病院の付き添いを面倒に感じるなんておかしい」「育ててもらった恩がある」なんて思ってしまうと、自分の気持ちに蓋をしてしまうこととなります
しかし、どれだけ親を思っての行動であっても、人にはそれぞれの限界があります。
負担を感じるのは自然なことであり、それ自体に罪悪感を抱く必要はありません。



「付き添いで疲れちゃった……」という気持ちを受け入れることが大切ですし、信頼する家族などに話してみるのも良いでしょう
高齢になった親の病院付き添いの負担を軽減する方法
高齢になった親の病院に付き添うことになった場合、できるだけ負担を軽減するよう工夫しましょう。
- 1人で抱え込まず他の家族に相談する
- 介護保険(通院介助)を利用する
- 自費でヘルパーを頼む
- 介護タクシー・福祉タクシーを利用する
- 自治体のサービスを利用する
- 訪問診療を利用する
それぞれ詳しく解説していきます。
1人で抱え込まず他の家族に相談する
まず、最初に考えたいことは、誰かに頼ることです。
親の付き添いをずっと1人で担っていると、心身ともに疲れてしまいます。



特に、兄弟姉妹がいる場合「手伝ってほしい」と素直に伝えるだけでも、気持ちがぐっと楽になることがあります
兄弟姉妹同士ですべてを平等に負担することが難しくても「遠方で付き添えない代わりにガソリン代を負担する」などと申し出てもらえることもあるでしょう。
また、自分だけで情報やスケジュール管理をすることが難しければ、家族LINEや共有カレンダーを導入し、通院予定や診察内容を共有するのもおすすめです。
介護保険(通院介助)を利用する
親が要介護認定を受けている場合、介護保険制度の中で「通院等乗降介助」というサービスを利用できる場合があります。
通院等乗降介助とは、通院の際の車の乗り降りや、病院内での移動などをヘルパーがサポートしてくれるものです。
ただし、病院内での診察付き添いや待ち時間の同席は対象外であることが多いため、介護保険サービス事業所と事前にサービス範囲や内容をしっかり確認しておきましょう。



実家と病院が離れており、移動が一番の負担になっている方には、特に有効なサポートになるはずです
自費でヘルパーを頼む
介護保険ではカバーできない部分については、自費サービスでの対応も選択肢のひとつです。
最近では、病院付き添い専門のサービスや、短時間から依頼できる家事・介護代行サービスなども増えてきています。
費用は1時間あたり2,000〜5,000円程度とサービスによって幅がありますが、以下のような対応まで行ってくれるサービスもあります。
- 診察内容を一緒に聞いてもらえる
- 薬の受け取りまで代行してくれる
親の通院回数が多く、すべてに付き添えない場合や、仕事と付き添いの両立が難しい方は、利用を検討してみても良いかもしれません。
介護タクシー・福祉タクシーを利用する
付き添いが必要な理由が移動手段のみであれば、介護タクシーや福祉タクシーの利用で事足りる場合もあります。
これらのサービスでは、車いすのまま乗車できたり、乗り降りや病院内の移動を介助してくれる運転手が同乗していたりと、高齢者に優しい設計となっているのが特徴です。
ただし、介護タクシーは、要介護認定を受けていることが利用条件になることも多いので、事前に利用条件を確認しておきましょう。



福祉タクシーであれば、自費で利用できるため、要介護認定がなくても利用できる場合があります。
また、事前予約が必要なことが多いため、定期的な通院の場合はスケジュールを立てて計画的に利用しなければなりません。
自治体のサービスを利用する
多くの自治体では、高齢者の通院支援や外出支援サービスを提供しています。
例えば、通院支援バスなどを用意している自治体もあり、対象者は無料または低額で利用できる場合があります。



自治体と民間バスが協働でシルバーパスを発行しているところもあるので、利用していきましょう
また、地域包括支援センターに相談すると、地域に根ざした民間サービスやボランティア団体による付き添いサポートなどを紹介してくれることもあります。



親が住んでいる自治体の公式サイトや高齢福祉課で情報を集めてみると、思わぬ支援策が見つかることもあるでしょう
病院の付き添いに限らず、親の見守りや介護については、家族だけで解決しようとせず、まずは困っていることを各窓口に相談してみることが大切です。
訪問診療を利用する
通院そのものが大きな負担となっている場合には、医師が自宅を訪問して診察を行う訪問診療の利用も選択肢に入ります。
特に、慢性的な疾患の経過観察や、寝たきり・認知症などで移動が困難な高齢者には、有効なサービスといえるでしょう。
高齢化に伴い、訪問診療を行う医療機関は年々増えており、対応地域や診療科も広がっています。
定期的な訪問に加え、体調の急変時に臨時訪問をしてくれるケースもあり、通院による負担を大幅に減らすことができるでしょう。



医療費は保険適用の対象となるため、経済的な負担も比較的抑えられます
病院付き添いが必要になる前に行っておきたいこと
高齢の親の通院付き添いは、ある日突然始まることも珍しくありません。
だからこそ、いざという時に慌てないためにも、以下のような方法で事前に対策しておくことをおすすめします。
- 親と定期的に連絡を取り合う
- 家族間で情報共有をしておく
- 自治体や介護サービスの情報を集める
それぞれ詳しく解説していきます。
親と定期的に連絡を取り合う
最も基本的で大切なことが、親と定期的にコミュニケーションを取っておくことです。
普段から、電話やLINEなどで定期的に連絡を取っておけば、小さな体調の変化や生活の様子にも気付きやすくなるでしょう。
例えば、「最近足元がふらつくようになった」「病院に行こうか迷っている」など、ちょっとした会話の中に体調や不安のサインが含まれていることがあります。



サインに気付けたら、事前に移動支援や民間のサービスについて調べる余裕も生まれるはずです
家族間で情報共有をしておく
親の通院付き添いが必要になったときに備えて、普段から誰が対応するのか、診察内容をどう共有するのかなどを家族で共有しておくことも大切です。
一人っ子ではなく、兄弟姉妹がいる場合は特に、「誰がどこまでやるか」「何を把握しておくべきか」を話し合っておくことが重要です。
例えば、以下のような情報は事前に共有しておくと安心です。
- 主治医の名前・診療科・病院の場所
- 持病や服用中の薬の内容
- 健康保険証や診察券の保管場所
- 通院スケジュールや次回予約
- 万が一の連絡先(本人・家族・医療機関)
情報共有には、共有カレンダーやクラウドメモアプリ(Google Keep、LINEノートなど)を使うと便利です。



誰か1人に情報が偏らないよう、全員がアクセスできる状態をつくっておくと、いざというときスムーズに対応できますし、不公平感も生まれにくくなります
自治体や介護サービスの情報を集める
親の年齢や健康状態によっては、将来的に介護が必要になる可能性もあります。
病院付き添いが「一時的な支援」ではなく「継続的なサポート」となったときに備えて、今のうちから自治体の支援や介護サービスの情報を集めておくことを強くおすすめします。
例えば、親に介護が必要になると、以下のような情報が必要となります。
- 自治体の高齢者外出支援(通院送迎サービス、タクシー助成券など)
- 要介護認定の申請方法と流れ
- 地域包括支援センターの相談窓口はどこか
- 通院付き添いが可能な介護保険サービスや民間サービス
- 地域の訪問診療対応医療機関の情報
これらの情報は、親が元気なうちに一緒に確認しておくとスムーズです。
本人も「こんなサービスがあるなら安心」と前向きになれることがありますし、後々のサービス利用の際にも「事前に話していたこと」として受け入れやすくなるでしょう。
高齢になった親の病院付き添いについてよくある質問
最後に、高齢になった親の病院付き添いについて、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 親の通院付き添いに疲れてしまうのは普通ですか?
-
親の通院付き添いの際に疲れてしまうのは、ごくごく普通のことです。
通院付き添いはただ一緒に病院に行くだけではなく、 親の体調を気遣いながら、病院の予約やスケジュール調整、仕事や育児との両立などをしなければなりません。
実家や病院が遠方にある場合には、移動や待ち時間も負担となるでしょう。
- 高齢になった親が病院に1人で行けないときにはどうすれば良いですか?
-
親が1人で通院できなくなった場合、家族が付き添う以外にもいくつかの選択肢があります。
- 介護保険サービス(通院等乗降介助)
- 自費による移動支援サービスの利用
- 介護タクシー・福祉タクシーの活用
本人の状態や経済状況に適した方法を選択しましょう。
- 親の入院時には付き添いが必須ですか?
-
近年では、入院中に家族が付き添うことが「原則不要」とされている病院が増えています。
特に、大規模病院や急性期病院では、付き添い不要の方針が一般的です。
ただし、付き添い不要の病院であっても着替えの洗濯や必要なものの買い出しなどは家族が行う必要があります。
【まとめ】一人で抱え込まず介護サービスの利用を検討しましょう
親の病院付き添いは、親が少しでも健康的に暮らしていくために大切なことである一方で、付き添う側にとって負担となる場合もあります。
親の通院に付き添いをすることとなった際には、1人で抱え込まず、家族で協力し合ったり、介護保険や自治体サービス、訪問診療などの支援を活用したりすることも検討しましょう。
特に、一人っ子ではなく、兄弟姉妹がいる場合には、普段から情報を共有しておき、無理のない範囲で親の生活をサポートしていくことが大切です。
このブログでは、高齢になった親のための見守りサービスや見守りカメラを紹介していきます。



ここまで読んでいただき、ありがとうございました
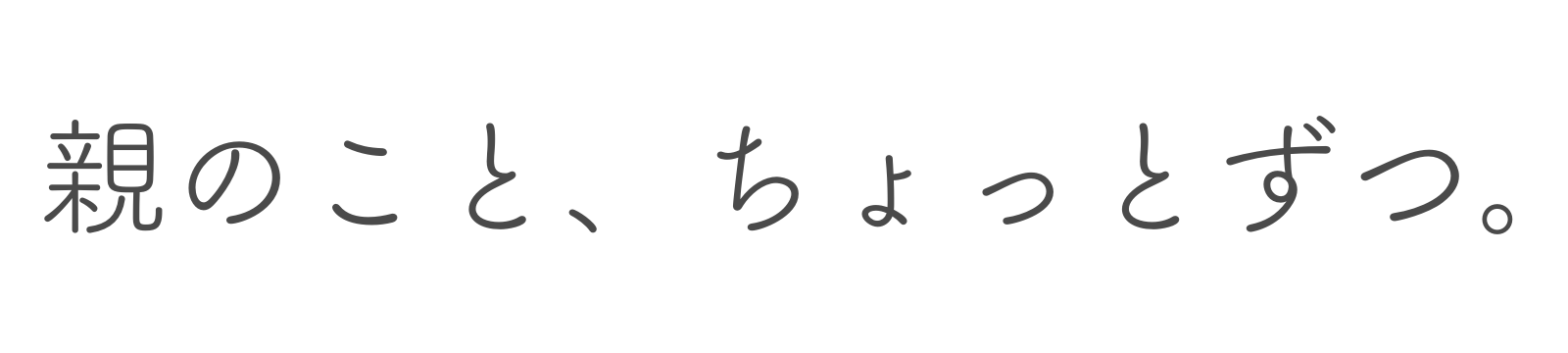
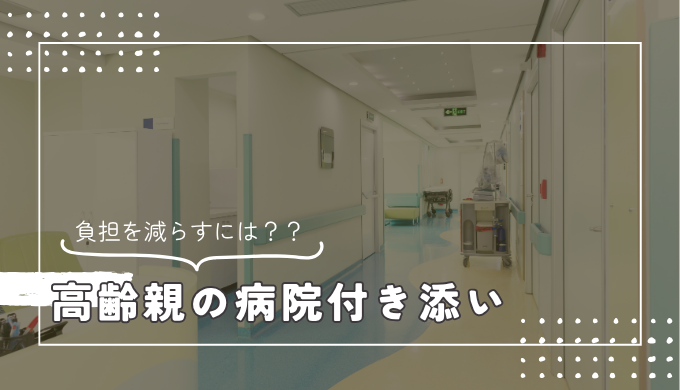


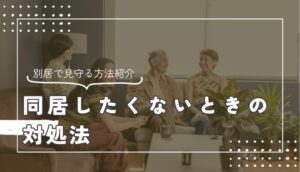
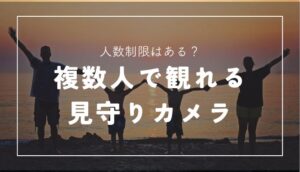

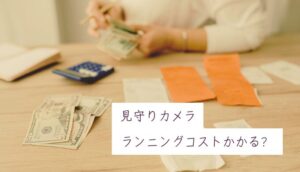
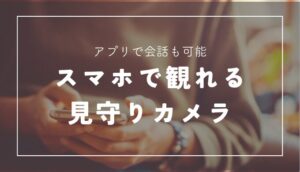
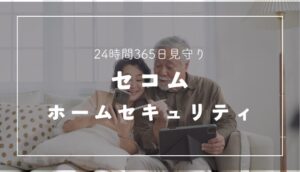
コメント