 お悩み
お悩み離れて住む親が高齢になってきたけど、同居しなきゃだめかな……



同居できない距離ではないけど、職場も遠くなるし、子供も転向しなければならなくなる……
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、高齢になった親と同居したくない理由や別居で親を見守る方法について紹介していきます。
- 高齢になった親と同居したくない理由
- 高齢になった親と同居するメリット・デメリット
- 高齢になった親と同居せず暮らしを見守る・サポートする方法
高齢の親が気がかりでも、物理的な理由や精神的な理由で「同居は難しい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
血のつながった親子であっても、生活スタイルや価値観の違い、介護負担への不安など、一緒に暮らすには様々なハードルがあります。
「親が高齢になったから絶対に同居しなきゃダメ」と考えるのではなく、見守りカメラやサービスなどを導入し、別居でも親の暮らしをサポートすることも検討しましょう。
本記事では、高齢になった親と同居したくない理由から、同居のメリット・デメリットを解説していきます。
高齢になった親と同居したくない3つの理由
高齢の親の生活を心配しつつも「できれば同居は避けたい」と考える人は決して少なくありません。
親子といえども、それぞれの生活があり、価値観も異なるため、同居によって生じるストレスやトラブルが起きる恐れがあります。
高齢になった親と同居したくない理由は、主に以下の通りです。
- 親と子供世代で生活スタイルが合わない
- 親子で仲が悪い・価値観が合わない
- 親が実家を離れたくないと主張する
それぞれ詳しく解説していきます。
親と子供世代で生活スタイルが合わない
親世代と子供世代では、日常の生活リズムや衛生感覚、食事の好み、テレビの音量など、細かな違いが多く存在します。
例えば、親は早寝早起きで1日中テレビをつけて過ごすのが普通でも、子供世代は夜遅くまで忙しく過ごし、自宅では静かに過ごしたいと考える場合もあるでしょう。



些細なことでも、毎日の積み重ねで不満や摩擦が大きくなり、結果的に家族関係に悪影響を及ぼすこともあります
親子で仲が悪い・価値観が合わない
そもそも、昔から親とあまり上手くいっていなかったり、あるいは一緒にいると喧嘩が増えたりすることもあります。
「親がいつまでも子供扱いして干渉してくる」などといった場合には、同居しても精神的に参ってしまう可能性もあるでしょう。
親が実家を離れたくないと主張する
子供側が親を心配して同居を提案したとしても、親が実家や地元を離れることに拒否反応を示すケースもあります。
特に、高齢になると、住み慣れた土地や近所付き合いが大きな安心材料となることもあるでしょう。
年齢を重ね、環境の変化に対応することが難しくなり、同居に抵抗感を示すこともあるはずです。
高齢になった親と同居するメリット
「同居は大変そう」というイメージが先行しがちですが、高齢の親と暮らすことにはメリットも存在します。
- 親の暮らしを見守れる
- 親が元気なうちは互いに協力し合える
- 親が生活費・住居費を分担してくれれば経済的に楽になる
- 親を扶養に入れれば所得税・住民税を節税できる
それぞれ詳しく解説していきます。
親の暮らしを見守れる
高齢になった親と同居する最大のメリットは、親の様子を日常的に見守れるという安心感です。
一緒に暮らしていれば、体調の変化や生活の異常にもすぐに気付けますし、高齢者の事故も防ぎやすくなります。
例えば、同居して毎日会話していれば、以下のような日常生活の些細な変化も見逃しにくくなるはずです。
- 最近物忘れが多い
- 同じ話を何度もする
- 食事量が減っている
- 足元がおぼつかない
また、通院や服薬の管理など日常生活のサポートもしやすくなるので、病気の早期発見や予防にもつながるでしょう。
特に、認知症の初期症状は、離れて暮らしていると見落としやすいのですが、実際には「ちょっとした変化」に家族が気付くことが何より重要です。
親が元気なうちは互いに協力し合える
親が高齢になってきてもまだ元気でいるのであれば、家事や育児などの面でお互い協力できることもあるでしょう。
例えば、共働き家庭であれば、親が子供のお迎えや夕食の支度を手伝ってくれることもあり、非常に助かる存在になります。



習い事や保護者会などに祖父母が出席されるケースも、増えてきています!
親も同居したからといって、子供世代に家事を任せきりにすると、自分でできることがどんどんなくなってしまう恐れがあります。
孫と関わることで、孤独感や無気力感を防ぎ、心身の健康を保ちやすくなるでしょう。
親が生活費・住居費を分担してくれれば経済的に楽になる
親と同居することで、家計の負担が軽くなることもあります。
例えば、親が年金収入の一部を生活費に充ててくれる場合、光熱費や食費の一部がカバーされ、世帯全体の支出を抑えられる可能性があります。
また、実家をリフォームして二世帯にしたり、親の土地に子供世帯が家を建てたりすれば、住居費の節約につながるケースもあります。
住宅ローンの支払いや子育てで出費がかさむ子供年代にとって、生活費や住居費の分担は大きなメリットとなるはずです。
親を扶養に入れれば所得税・住民税を節税できる
親を扶養親族として申告すれば、所得税や住民税の控除が受けられるという税制上のメリットもあります。
ただし、親を扶養に入れられるかは、同居だけが条件となっているわけではなく、親が一定以下の所得でなければなりません。
高齢になった親が介護が必要な状態であれば、医療費控除や障害者控除を適用できる場合もあります。



これらの制度を活用すれば、所得税や住民税を節税できる可能性があります
高齢になった親と同居するデメリット
高齢の親の生活を支える手段として、同居はひとつの選択肢ですが、メリットだけではなくデメリットもあることを理解しておきましょう。
- 親子共にストレスを感じやすくなる
- プライバシー・距離感を保ちにくくなる
- 介護が必要になったときの負担が大きい
それぞれ詳しく解説していきます。
親子共にストレスを感じやすくなる
高齢になった親と同居すると、親世代・子供世代ともにストレスを抱えてしまう恐れがあります。
親世代と子供世代では、生活リズムや価値観、家事のやり方など、あらゆる面で違いがあるからです。
例えば、親が家事や育児の方針について口出しをしてくることで子供がストレスを感じたり、逆に子供の行動に対して親が「こんなはずではなかった」と不満を抱いたりすることも少なくありません。
プライバシー・距離感を保ちにくくなる
同居すれば当然、親子の生活空間が重なり、プライバシーの確保が難しくなります。
二世帯住宅の種類にもよりますが、一部共用型や完全共有型の場合は、お風呂やトイレなどを共有することになり、利用時間や使い方などで気を使わなければならない場面が増えてくるはずです。
介護が必要になったときの負担が大きい
高齢の親と同居していると、介護が必要になったときに、介護が自然と同居家族に集中してしまう傾向があります。
「近くにいるから」といって、介護の大半を担うことになると、同居家族の負担が重くなってしまいます。
結果として、他の兄弟姉妹との間に不公平感が生まれたり、介護による離職をせざるを得ないケースもあるでしょう。
【体験談】私も実両親・義両親と同居はしたくありません
私の実両親や義両親はまだまだ元気なのですが、将来的にもできたら同居はしたくないなと考えています。
私というか夫がすでに自宅を購入しているのも理由のひとつですし、私の母が姑と同居しており、関係が良くなかった様子を間近で見ていたのも理由のひとつです。
本章では、私が実両親や義両親とできたら同居したくない理由を紹介していきます。
私の母は姑と同居しており関係が悪いのを見てきた
私の母は、私が子供の頃から父方の祖母(母にとっての姑)と同居していました。
祖母は仕事一筋で私が子供のときはまだ仕事をしており、在宅時間は短かったのですが、それでも母と意見が衝突しているのを何度も目にしてきました。
個人的には、祖母と母が揉めるよりも、それをきっかけにして父と母が言い争うのを見るのが辛かったのを記憶しています。
母も勝ち気な性格で祖母に対し「夫は選べるけど、姑は選べない。お母様は◯◯さん(父)と結婚して付いてきただけですから」などと言っていましたが、幼少期に本当にその通りだなと感じました。
結婚をする際に、姑になる人物を選ぶことはできませんし、嫁になる人物を選ぶことも今の時代ではなかなかできないはずです。



私は自分で選んだ家族(夫)や自分が産んだ家族(子供たち)をまずは大切にしたいので、できる限り同居はしたくありません
同居すると兄弟姉妹の実家がなくなることになる
同居を避けたいと思う理由のひとつに、同居をしてしまうと他の兄弟姉妹の実家がなくなり、寂しくないだろうかというものがあります。
私も夫も3人兄弟の第一子であり、それぞれ弟・妹がいます。
例えば、私が実両親や義両親と同居したら、妹・義妹が里帰り出産しにくくなるのではないか、帰省しにくくなるのではないかと思うのです。
実家は、誰にとっても自分のルーツであり、安心して帰れる場所であってほしいものです。



だからこそ、できるだけ親とは同居をせず、別居だけど近い距離で見守っていきたいと考えています
高齢になった親と同居せず暮らしを見守る・サポートする方法
高齢になった親の生活を見守るには、必ずしも同居しなければならないわけではありません。
以下のような方法を利用すれば、離れて暮らしていても、親の生活をサポート可能です。
- 見守りカメラ・サービスを利用する
- 在宅の介護保険サービスを利用する
- 介護保険外のサービスを利用する
- 施設に入所してもらう
それぞれ詳しく解説していきます。
見守りカメラ・サービスを利用する
見守りカメラやセンサーなどのICT機器を活用すれば、別居でも親の生活を見守りやすくなります。
見守りカメラであれば、離れて住む親の様子を映像で確認できますし、リアルタイムの様子も確認可能です。
他には、冷蔵庫やドアなどに設置できるセンサーを活用すれば、親の生活スタイルもある程度把握しやすくなります。



「朝から冷蔵庫1回も開けてないけど大丈夫かな?」など、親の変化や事故にもすぐ気付きやすくなるでしょう
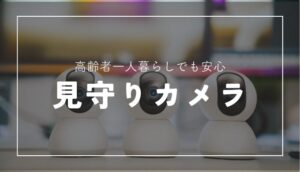
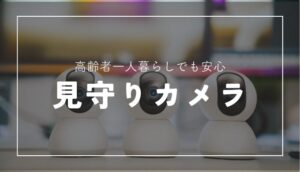
在宅の介護保険サービスを利用する
要介護認定を受けた高齢者であれば、介護保険を利用して様々なサービスを受けられます。
要介護認定や介護保険が適用されるサービスと言われると、施設入所を考えがちですが、実際には以下のような在宅で利用できるサービスも用意されています。
- 訪問介護
- 訪問看護
- デイサービス
- ショートステイ
これらのサービスを上手に利用すれば、専門職の支援を受けつつ、親の生活を支えられます。



実際に、私の地域にも子供世代は近距離別居しつつ、一人暮らし+介護サービスで乗り切っている高齢者も多くいます
介護保険外のサービスを利用する
要介護認定とならない場合には、介護保険外の自費サービスの利用も検討しましょう。
介護保険外のサービスは全額自費となる一方で、介護保険では補えない多様なニーズに対応できるようになっています。
- 家事代行
- 高齢者向けの宅食サービス
- 買い物代行・付き添い
- 通院付き添い
例えば、大きな買い物が負担になってきた場合や火の始末が不安になってきた場合には、宅食や買い物代行を依頼して乗り切るのも選択肢のひとつです。



サービス選びや契約の際に子供がサポートしてあげれば、親も利用しやすくなるでしょう
施設に入所してもらう
在宅での生活が難しくなった場合には、子供世代との同居だけでなく、特別養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの施設への入所も検討しましょう。
介護は子育てと違って終わりはなく、在宅介護の負担は非常に大きいものとなるからです。
施設に入所してもらえば、専門職に介護をしてもらえますし、24時間体制でサポートしてもらえます。
「世話になったから同居したい」と安易に考えるのではなく、親に合った施設を探したり、入所手続きをしたりすることも立派な親孝行のひとつです。
高齢親と同居したくないときによくある質問
最後に、高齢になった親と同居したくないときによくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 親と同居しない理由は何がありますか?
-
親と同居しない理由は、以下のように、様々なものが考えられます。
- 親と子供世代で生活スタイルが合わない
- 親子で仲が悪い・価値観が合わない
- 親が実家を離れたくないと主張する
介護疲れや介護が原因の離職を避けたいと思い、同居を選択したがらない方もいます。
- 高齢親はいつまで一人暮らしできますか?
-
高齢になった親が一人暮らしを続けられるかどうかは、年齢そのものよりも健康状態や判断力、生活環境が大きなカギを握ります。
例えば、自分で買い物に行けて家事もこなせるのであれば、80代でも安心して一人暮らしを続けられるでしょう。
一方で、子供たちは遠方に住んでいて頼れず、火の始末や物忘れなど不安な点が増えてきた場合には、今の状態で一人暮らしを続けることが難しい場合もあります。
- 実親と同居して上手くいかない理由は何ですか?
-
実の親との同居であっても、関係がこじれるケースは少なくありません。
むしろ、血のつながりがあり、遠慮がない分、感情的な衝突が起きやすいのが実親との同居の難しさです。
実両親との同居が上手くいかない理由としては、以下のようなものがあります。
- 親が生活に過干渉する
- 逆に子供側が親の行動を否定し、親が居場所をなくす
- 世代間の価値観の違いが顕著で、日常的に小さな衝突が起きる
一つひとつは小さな摩擦であっても、長期間にわたり続くと互いに負担となってしまうことも多いのでご注意ください。
実の親子であっても、今は違う家庭を持っていると考え、適度な距離感を保つことが大切です。
【まとめ】同居しなくても親の介護や見守りをすることは可能です
親と同居するかどうかは、感情だけでなく生活環境・家族関係・将来の介護まで見据えた総合的な判断が必要です。
同居をすれば、親の暮らしを見守りやすくなったり、生活費や住居費を抑えられたりする一方で、親子共にストレスとなる可能性もあります。
場合によっては、無理に一緒に暮らすのではなく、見守りカメラや在宅支援などのサービスを活用することも検討しましょう。
親を想う気持ちがあるからこそ、無理のない形で見守る選択をする」ことは、立派な親孝行のひとつです。
このブログでは、高齢になった親の暮らしを見守る方法やちょうど良い距離感の保ち方について解説していきます。



よろしければ、他の記事もお読みいただけますと幸いです
ここまで読んでいただき、ありがとうございました
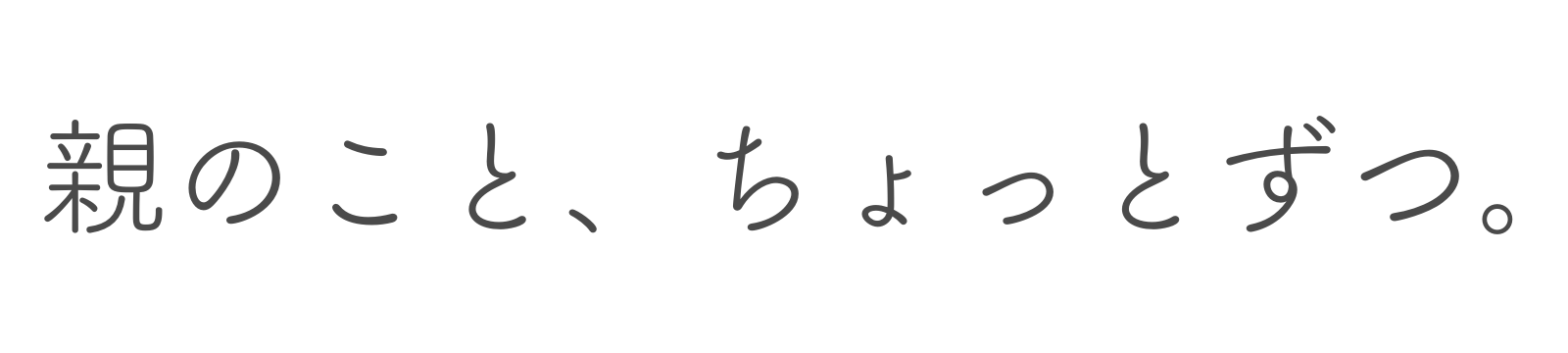
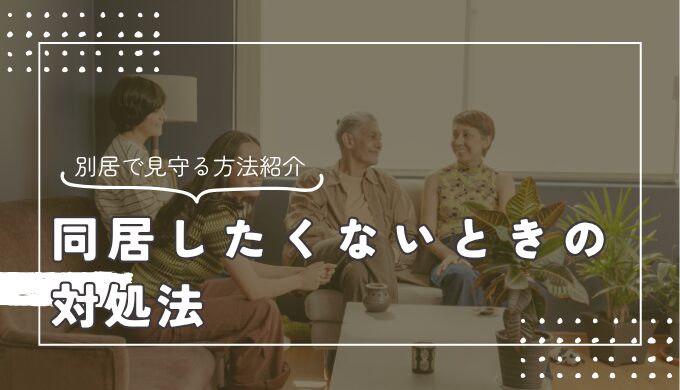


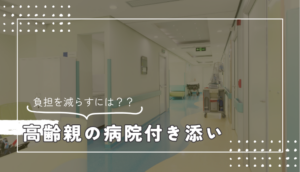
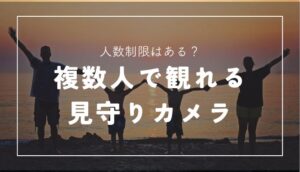

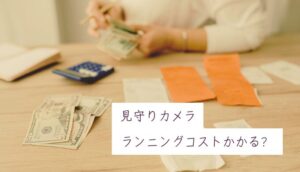
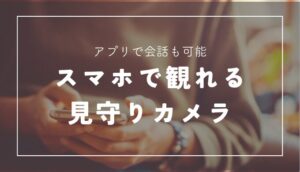
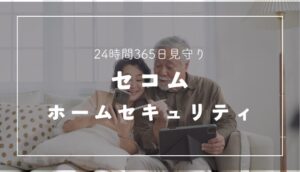
コメント