 お悩み
お悩み高齢になった親の様子をどれくらいの頻度で見にいけば良いかな?



これまでは長期休暇しか会っていなかったけど、頻度を増やした方が良いのかな
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、高齢になった親と会う頻度や離れて住む親の暮らしを見守る方法について解説します。
- 高齢になった親と会う頻度はどれくらいが良いか
- 高齢になった親の暮らしを見守る方法
離れて暮らす高齢の親のことを考えると、「どのくらいの頻度で会いに行けばいいのか」「連絡はどれくらい取るべきか」と悩む方は多いのではないでしょうか。
子供世帯は仕事や子育てとの両立で頻繁な帰省が難しく、親の暮らしは不安だが、なかなか会えないといったケースも珍しくありません。
親に会う頻度に正解はなく、親の年齢や実家との距離、子供世帯の忙しさなどでも変わってきます。
頻繁に会うことができず不安な場合には、見守りカメラやサービスを導入しても良いでしょう。
本記事では、高齢の親と会う頻度や離れて住む親の暮らしを見守る方法を解説していきます。
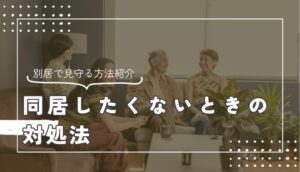
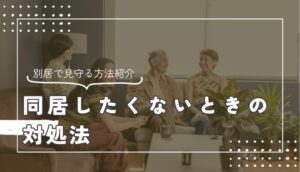
高齢になった親と会う頻度はどれくらい?
実家にいる親とどれくらいの頻度で会うべきかは、実家との距離や親の年齢、親との関係などによっても異なります。
もう少し会いたいと感じている方もいるでしょうし、家事や育児、仕事などが忙しくこれ以上会うのは負担になると思っている方もいるでしょう。
「高齢者と子どもの交流ー意識と実態にみる日本の特徴ー」という調査によると、高齢者と別居している子供が親世帯に会う頻度は以下のような結果になっています。
| ほとんど毎日 | 20.3% |
|---|---|
| 週に1回以上 | 30.9% |
| 月に1〜2回 | 26.8% |
| 年に数回 | 18.8% |
| ほとんどない | 3.1% |
参考:高齢者と子どもの交流ー意識と実態にみる日本の特徴ー|お茶の水女子大学基幹研究院
高齢親と会う頻度に正解はなく、以下のような観点で、無理のない頻度を見つけていくことが大切です。
- 親の健康状態や年齢
- 居住地からの距離
- 自分や家族の予定(子育て・仕事など)
- 親自身が会いたいと思う頻度
例えば、元気なうちは年に数回でも十分かもしれませんが、病気や認知症の兆候が見られたら、会う頻度を増やす方が安心です。
一方で、実家と自宅が飛行機の距離にあり、頻繁に会うのが物理的に難しい場合もあるでしょう。
そのようなケースでは、見守りカメラや見守りサービスを併用することで、日常の様子を把握しやすくなるはずです。
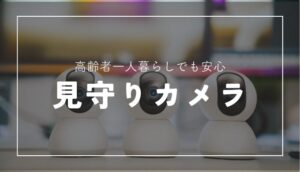
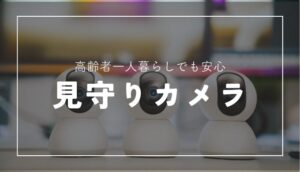
【体験談】親と会う頻度は年数回
私の実両親は義両親はまだ60代前半と若く、全員仕事を続けています。
実家も自宅も都内にあるのですが、親と会う頻度は年数回程度です。



平日は子供の学校や仕事があり、休日は子供の習い事があるため、年に数回の長期休みに帰省する程度となっています
本章では、私が親と会っている頻度を一例として紹介していきます。
【実両親】母のパートと子供の休みが合う長期休暇が中心
実母は現在も週に数回、近所のコンビニでパートをしており、休みは平日しかありません。
子供と実母の休みが合わないため、会うタイミングは主に子供の長期休暇に数日程度となります。



子供が小学校に通うまでは、病院の付き添いを母に頼むこともありました
しかし、良くも悪くも新型コロナウイルス感染症の影響により夫の会社で在宅勤務が普及したため、在宅勤務や有給を活用して夫婦で子供の病院関係の幼児もこなせるようになりました。
帰省自体は年に2〜3回ほどですが、1回の滞在を3日と多少長めにとることで、ゆっくり話をしたり、一緒に買い物に出かけたりできています。
帰省中は、家電の不調を確認したり母親の話をじっくり聞いたりと、さりげなく生活の変化にも気を配っています。
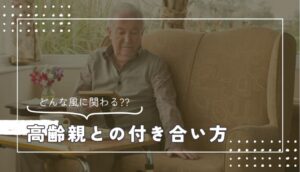
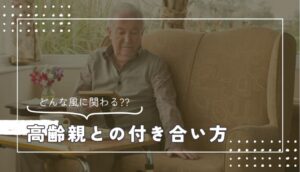
【義両親】長期休暇や3連休などを使って帰省
義実家は都内ですが車で1〜2時間ほどかかるので、こちらも長期休暇を中心に帰省しています。
以前は祝日があり3連休になるときなど、帰省していたのですが、子供の習い事が増えたため帰省頻度が減りました。
義実家は義祖母がまだ2人とも存命なこともあり、義両親も「自分たちが義祖母を支えないと」と日々忙しそうにしています。



義祖母が生きていてそちらのサポートが必要なことや、義両親ともに60代なこともあり、まだまだ元気でこちらのサポートは必要としていなさそうです
高齢になった親の暮らしを見守る方法
親が高齢になると生活のサポートや暮らしの見守りが必要となります。
しかし、サポートや見守りは必ずしも会わなければならないわけではなく、離れて住んでいてなかなか会えなくても行うことが可能です。
- LINEなど使いやすいコミュニケーションツールを活用する
- 見守りカメラ・サービスを利用する
- 何気ない話をこちらからもするようにする
- 親の「ちょっとなぁ」と思う発言は聞き流す
- 趣味サークルやボランティアなど親の居場所作りに協力する
- 自治体・民間の介護サービスを調べておく
本章では、高齢になった親の暮らしを離れていても見守る方法や見守り時の子供世帯の負担を減らすコツを紹介していきます。
LINEなど使いやすいコミュニケーションツールを活用する
まず取り入れやすいのが、LINEなどの無料通話アプリです。
電話やメールよりも気軽に連絡できますし、既読機能があるので、生存確認にもなります



妹が結婚し、家を出てからは実両親+兄弟姉妹でグループLINEを作り、こまめにやりとりしています
LINEであればビデオ通話もできるので、なかなか帰省できない場合のコミュニケーションにも役立つでしょう。
見守りカメラ・サービスを利用する
実家が遠方にありなかなか会えない場合には、何かあったときに備え、見守りカメラや見守りサービスを導入するのも良いでしょう。



我が家では、実家の玄関に見守りカメラを設置しています
もともとは実家にいるペットの様子を見るために設置したものですが、玄関にあることで親の様子を確認できる点も魅力です。



転倒や体調不良などの異変にすぐ気付きたいのであれば、玄関だけでなくリビングや寝室に設置するのもおすすめです。
他には、センサー付きの家電や宅食サービスを利用することで、離れて住む親の安否確認を確認するのも良いでしょう。
いずれも、親のプライバシーを尊重しながら検討していくことが大切です。
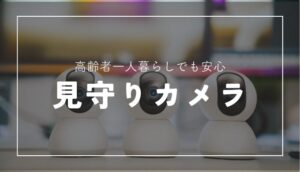
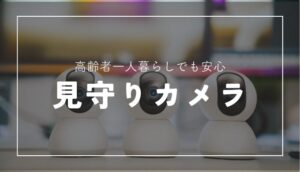
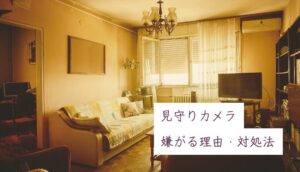
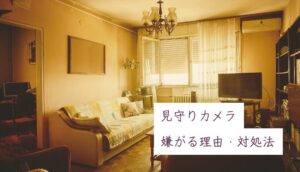
何気ない話をこちらからもするようにする
親の様子を知りたいとき、つい「体調は?」「病院は行ってる?」とこちらから細かく聞きたくなりますが、相手からすると詮索されていると感じたり負担に思ったりすることもあるでしょう。
私の場合、親と良好な関係を保つためにも、こちらからも他愛のない話をするようにしています。



孫の話題や私が学生時代の友人と会った話などを伝えると、親も自分のことを話してくれるようになります
親の「ちょっとなぁ」と思う発言は聞き流す
高齢の親とのやり取りでは、ときに「昔はよかった」「テレビのあの人は嫌い」などネガティブな発言が気になることもあります。
それに正面から反論すると、親も反発してきて、余計に話すのが億劫になることもあるでしょう。
私の場合は「そうなんだ〜」と軽く流したり「それより、この前ね……」と話題を変えるようにしています。
生活で見守りが必要な点は確認しつつ、細かい会話や親の嗜好、価値観についてはあえて深く立ち入らないことも必要だと感じます。
趣味サークルやボランティアなど親の居場所作りに協力する
高齢になって家にこもりがちになると、体力はなくなり、認知機能もどんどん衰えてしまいます。
とはいえ、親に対して「もっと外に出なよ」「人と話すようにしなね」と伝えても、難しい場合もあるでしょう。
そのようなケースでは、子供世帯にとっては少し手間ですが、無理にすすめるのではなく、興味を持ちそうなことを一緒に探す姿勢が大事です。



例えば、地域のボランティアや習い事を探してみたり、一緒に参加してみるのも良いでしょう
私の友人の話になりますが、帰省のタイミングで近所の公園や野山のバードウォッチング+散歩の会に親子で参加してみたそうです。



親にとっては近所の人と交流する機会になるし、友人にとっては運動不足解消になったと話していました
自治体・民間の介護サービスを調べておく
元気なうちは「まだいいか」と先延ばしにしてしまいがちですが、いざというときに備えて、住んでいる地域の介護サービス情報は早めに把握しておくと安心です。
- 要介護認定の申請はどこにすれば良い?
- かかりつけ医が診断書を書いてくれない場合、信頼できる精神科の病院はどこにある?
- 配食サービスはある?
- 通所リハビリやデイサービスの利用方法は?
- 要介護認定を受けていないときでも自費で使えるサービスはある?
上記の情報はネットでもある程度調べられますが、地域包括支援センターに相談すると、お住まいの地域や両親の状況に合ったアドバイスをもらえるはずです。
いざというとき慌てないように、情報だけでも少しずつ整理しておくと、将来的な選択肢の幅が広がるでしょう。
高齢になった親と会う頻度についてよくある質問
最後に、高齢になった親と会う頻度について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 離れて住む親と会う頻度はどれくらいが適切ですか?
-
結論から言うと、「これが正解」という頻度はありません。
それぞれの家庭事情や親の健康状態、居住地との距離などによって大きく異なるからです。
親子共に無理のない頻度で会うと良いでしょう。
- 高齢になった親との連絡頻度はどれくらいが適切ですか?
-
連絡頻度も親子の関係性や親の性格によって、ベストな回数は変わります。
一般的には、「週1回程度の連絡」がひとつの目安となります。
ただし、「頻繁すぎる連絡がストレスになる」という親もいれば、「毎日でも連絡がほしい」という親もいるので、親子ともに無理のない頻度を見つけていきましょう。
- 高齢になった親との会話にイライラする原因は何ですか?
-
高齢になった親と久しぶりに会話してイライラしたりモヤモヤしたりしてしまうことは、決して珍しくはありません。
高齢になると、認知能力や記憶力、気力の衰えにより、以下のような会話をしてしまう方も多くいるからです。
- 昔話や同じ話を何度も繰り返される
- ネガティブな発言や批判が多い
- 心配されすぎて、干渉されているように感じる
- こちらの生活や忙しさを理解してくれない
高齢の親との会話にイライラしてしまうときには、ある程度受け流してしまうのもおすすめです。
【まとめ】会う回数・頻度にこだわるのではなく小まめに連絡をするのがおすすめです
高齢の親と会う頻度や連絡頻度に正解はないので、なかなか会えなくても罪悪感を持ちすぎる必要はありません。
大切なことは会う頻度よりも「気にかけている姿勢」と「安心できるつながり方」です。
仕事や育児で忙しくなかなか帰省できない場合には、見守りカメラや見守りサービスを導入し、離れていても親の暮らしを見守る仕組みを作るのが良いでしょう。
見守りカメラやサービスだけでなく、LINEなどのツールも活用すれば、離れて住む親子でもコミュニケーションを取りやすくなるはずです。
このブログでは、高齢になった親の暮らしを無理なく見守る方法を紹介していきます。



ここまで読んでいただき、ありがとうございました
よろしければ、他の記事もお読みください
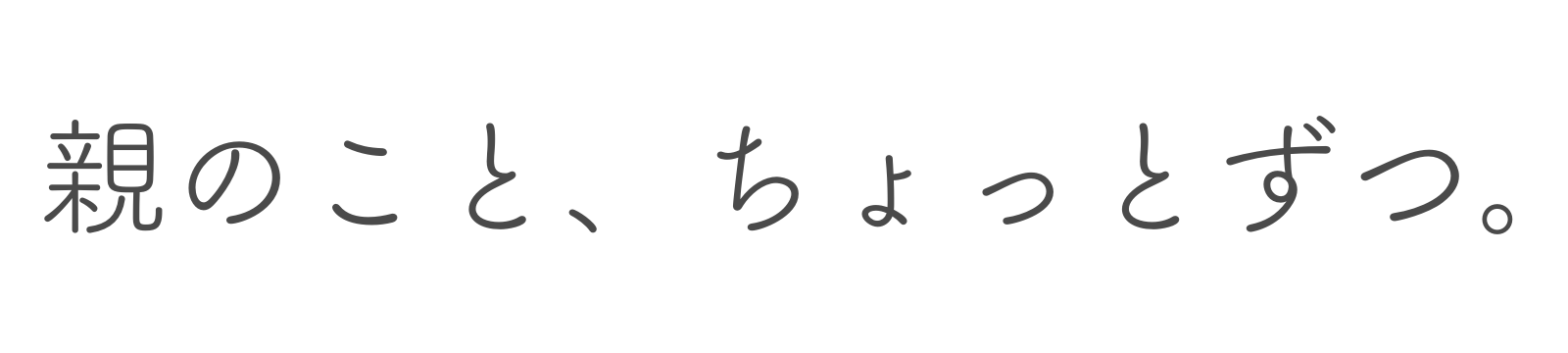
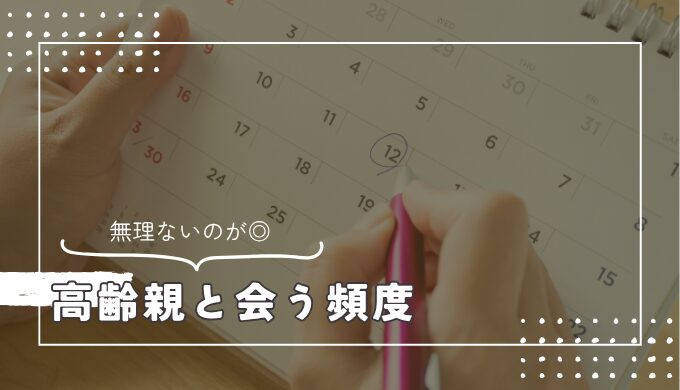

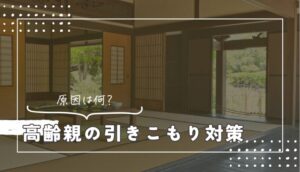

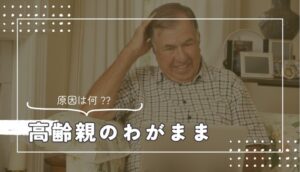
コメント