 お悩み
お悩み高齢になった親とどんな風に関われば良いか、わからなくなってきた……



話もかみ合わなくなってきたし、子供も祖父母に会うのを嫌がる……
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、高齢になった親と関わりたくないと思ってしまう原因と対処法を解説していきます。
- 高齢になった親と関わりたくないと思ってしまう原因
- 高齢になった親と上手く関わるコツ
高齢の親との関係や関わり方に悩む方は、決して少なくありません。
親の性格やこれまでの関係性によっては、「できれば関わりたくない」と感じてしまうこともあるでしょう。
親子とはいえ、それぞれの家庭に事情があるため、関係の築き方や距離の取り方に正解はありません。
また、親の心身の変化や子供世代の環境の変化によって、親との付き合い方が変わってくることも十分にあり得ます。
本記事では、高齢になった親と関わることに対するストレスや戸惑いの原因を整理し、無理のない距離感で関わるためのコツを紹介します。
高齢になった親と関わりたくないと思ってしまう6つの原因
親が高齢になってくると、心身や環境に変化があり、これまでと性格や態度が変わってしまうこともあるでしょう。
また、子供世代も家事や育児、仕事などで日々忙しく「親のことを気にかける余裕なんてない」「自分たちの生活でいっぱいいっぱい」と感じることもあるはずです。
高齢になった親と関わりたくないと思ってしまう主な原因は、以下の通りです。
- 仕事や家事・育児で忙しい
- もともとの性格が合わない・関係が良くなかった
- 孫との関わり方が合わない
- 親が高齢になるにつれて性格が変わってしまった
- 親がわがままを言うようになった
- 親の物忘れがひどくなってきた
それぞれ詳しく解説していきます。
仕事や家事・育児で忙しい
そもそも、現役世代は、仕事や家事、子育てに追われていることが多く、物理的にも精神的にも余裕がありません。
その中で「親のことまで手が回らない」と感じてしまうのは、ごく自然でしょう。



私も、平日夕方に親から連絡が来ると「今!?」と思ってしまうときがあります
特に、親が高齢になると、病院の付き添いや日常のサポート、ちょっとした愚痴への対応など、地味に時間を取られる場面が増えてきます。
親に悪気がないのはわかるものの、「また電話……?」「今は無理」と、心が離れていくこともあるでしょう。
もともとの性格が合わない・関係が良くなかった
もともと親子関係が良好でなかった場合、高齢になった親に対して「今さら関わりたくない」と感じてしまうこともあるでしょう。
以下のように、親に対して積み重なった感情がある場合には、無理に距離を縮めようとすること自体がストレスになることもあります。
- 過去に厳しく育てられた
- 傷つく言葉を言われた
- 価値観が根本的に合わない
年齢を重ねても、自分の中で整理しきれていない気持ちが残っていることは、決して珍しくありません。



親と関われない自分がおかしいのか……?と余計に罪悪感を持つのも辛いですよね
孫との関わり方が合わない
自分の子供(親から見た孫)に対する接し方が原因で、親との関係がぎくしゃくすることもあります。
例えば、子育ての方針に口を出してきたり、昔の価値観で押し付けてきたりする場合、意見がずれやすく親に関わりたくないと思ってしまうこともあるでしょう。
親が高齢になるにつれて性格が変わってしまった
「昔はもっと穏やかだったのに……」「最近、愚痴っぽくなってきた」と、高齢になってから親の性格が変わったと感じることもあります。
これは、加齢による脳の働きの変化や、身体の不調・孤独感などが原因になっていることもあると理解しておくと良いでしょう。
特に、急に怒りっぽくなった場合、認知症の初期症状である場合もあるのでご注意ください。



不安なことや気になることがあれば、地域の包括支援センターやかかりつけ医に相談してみるのもおすすめです
親がわがままを言うようになった
年齢を重ねると、心身の不調や環境の変化から不安が強くなり、一見するとわがままに見える言動が増えることがあります。
- 「これ買ってきて」
- 「今すぐ来て」
- 「〇〇してくれないと寂しい」
このような要求が頻繁になると、子供側としては負担感を強く感じますし、「なんでこんなにしてあげなきゃいけないの」と思ってしまうこともあるでしょう。
大切な親だからできる限り要求を受け入れてあげたいと思ってはいるものの、自分たちの生活への影響が大きくなると、距離を置きたくなるのも無理はありません。
親の物忘れがひどくなってきた
親の物忘れが増えてくると、同じ話を何度もされたり、約束を忘れられたりすることが増え、子供側が精神的に疲れてしまうことがあります。
「言ったのに覚えていない」「また同じ説明をしなきゃいけない」という繰り返しにストレスを感じ、会話やコミュニケーション自体を面倒に思ってしまうこともあるでしょう。
また、自分の子供(親から見た孫)が祖父母と話したがらなくなり、関わりが減ってしまうケースもあります。
高齢になった親と上手く関わるコツ
高齢になった親と関わる際には、親の心身の衰えや子供世代との生活環境の差を理解しておくことが大切です。
具体的には、以下のようなことを意識しておくと良いでしょう。
- 自分たち家族を最優先すると決めておく
- やってあげたいと思うことだけやってあげる
- 不満や愚痴は聞き流してしまう
- 高齢者の心身の変化・衰えを理解する
- 親が自分で楽しめる趣味を探してみる
- 介護や医療機関のサポートを受ける
それぞれ詳しく解説していきます。
自分たち家族を最優先すると決めておく
高齢の親との関わりでストレスを感じやすい方は、自分たち家族を最優先するとあらかじめ決めておくことで心が軽くなることがあります。
親の要望や不安にすべて応えようとすると、自分やパートナー、子供との時間を削られてしまいかねません。
優先順位を明確にすることで、「これは対応できる」「ここまでは無理」と冷静に線引きができるようになります。



親の要求に応えてあげられないのは、仕方がないと思えるだけでも楽になるはずです!
やってあげたいと思うことだけやってあげる
義務感や罪悪感から「やらなければならない」と自分を追い詰めてしまうと、親との関係はしんどくなる一方です。
逆に、「これは自分がしてあげたい」と思えることだけを選んで行動することで、納得感のある関わり方ができます。



これは、私も日々実践しています
自分が親や義両親のためにやってあげたいなと思うことだけをしていると、自分の気持ちも満たされますし、心から善意で動けるので親に対して「やってあげた感」も生まれません。
もちろん、親や義両親の要求すべてに応えることはできませんが、それでも自分がやりたくてやったことに対して感謝の気持ちを表現してもらえると嬉しくなります。
不満や愚痴は聞き流してしまう
親の話をすべて真面目に受け止めると、こちらが疲れてしまうことも多々あります。
特に、高齢になると不安や孤独から不満や愚痴が増えることもあるため、それらをいちいち真剣に受け止める必要はありません。
「そうなんだね」「大変だったね」と軽く受け流すくらいが、ちょうど良い距離感になることもありますし、正面からのアドバイスや批判より親が喜んでくれることもあります。



親が感情をぶつけてくるときこそ、こちら側は冷静に一歩引いて対応してしまいましょう
高齢者の心身の変化・衰えを理解する
子供にとってはいつでも親であると考えてしまいがちで、ついつい「昔はもっとしっかりしていたのに」と思ってしまうこともあります。
しkし、親が高齢になると心身ともに衰えてくることは自然ですし、それによって会話の内容や言葉の選び方が変わってくることも当然あります。
- 記憶力や判断力が落ちる
- 同じ話を繰り返す
- 体調の変化に敏感になる
上記のような高齢者特有の特徴を知っておくだけでも、子供世代のイライラを減らせるものです。



知識として理解しておくことで「なんでこんなこと言うの」ではなく「そういうものなんだ」と受け流せる余裕が生まれます
親が自分で楽しめる趣味を探してみる
親自身の楽しみや居場所があることで、子供世代への依存が減り、適切な距離感を保ちやすくなります。
- 趣味のサークル
- 家庭菜園
- 手芸
- ラジオ体操
- 地域の集まり・ボランティア
- 習い事
上記のような楽しみを見つけられれば、親も生きがいを見つけられるかもしれません。
最初は親も行きたがらなかったり、どんな集まりがあるかを調べられなかったりするかもしれません。
その場合は、子供世代がサポートや付き添いをしてあげ、徐々に親が楽しめるように工夫していきましょう。
介護や医療機関のサポートを受ける
高齢になった親の暮らしを家族だけですべて支えていくことには、限界があります。
必要に応じて、介護保険を使ったサービスや地域包括支援センターの相談窓口の利用もご検討ください。
また、認知症は初期症状であれば、治療や投薬で進行を遅らせることができる場合もあります。



最近、様子がおかしいなと思った段階で、かかりつけ医などに相談するのも良いでしょう
高齢になった親と関わりについてのよくある質問
最後に、高齢になった親との関わり方について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 親と縁を切ることはできますか?
-
「親子の縁を切る」という制度は、法律上は存在しません。
たとえ関係を断ちたいと考えても、民法上は親子関係が継続しており、互いに扶養義務や相続関係が残りますし、戸籍から親の情報を消すことはできません。
一方で、物理的もしくは心理的な距離を取ることは可能です。
親から離れて住み住所や連絡先を教えなかったり、親が何か言ってきても反応しなかったりすることはできるでしょう。
- 親の介護をしないと罪に問われますか?
-
原則として、子供には親に対する扶養義務がありますが、これは必ずしも同居や介護を強制されるものではありません。
扶養義務は自分たちでできる範囲で義務を果たせばよいとされているからです。
実家と職場が離れており、同居が難しい場合は必ずしも同居しなければいけないわけではありませんし、自分たちの生活が苦しい場合には親に援助をしなくても良いとされています。
- 高齢の親と同居していてストレスを感じるときにはどうすればいいですか?
-
同居によるストレスは、多くの人が抱える現実的な悩みです。
ストレスを感じるのは、むしろ当たり前であり、「ストレスを感じてはいけない」と自分を責めないようにしましょう。
むしろ、介護の一部を外部サービスに委託したり、短時間でも1人になれる空間や時間を確保したりといった小さな対策を日ごろからしておくと良いでしょう。
【まとめ】最初から無理なく付き合うことを意識してみましょう
高齢の親との関係に悩む原因としては、子供世代の多忙さや過去の関係性、親自身の変化など、様々な原因が考えられます。
だからこそ、無理に理想的な親子関係を目指すのではなく、自分たち家族を大切にしながら、できる範囲で関わることが大切です。
親との関わり方に悩んでしまうのであれば、自分が心からやってあげたいことだけを選び、それ以外のことは必要に応じて対応すると線引きをしてしまうのも良いでしょう。
高齢になってくると、心身の変化により愚痴っぽくなってしまうこともあるので、不満は受け流し、必要に応じて介護サービスや見守りカメラの活用なども検討していきましょう。
本ブログでは、高齢になった親との関わり方や見守りカメラ・サービスの紹介をしています。



ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
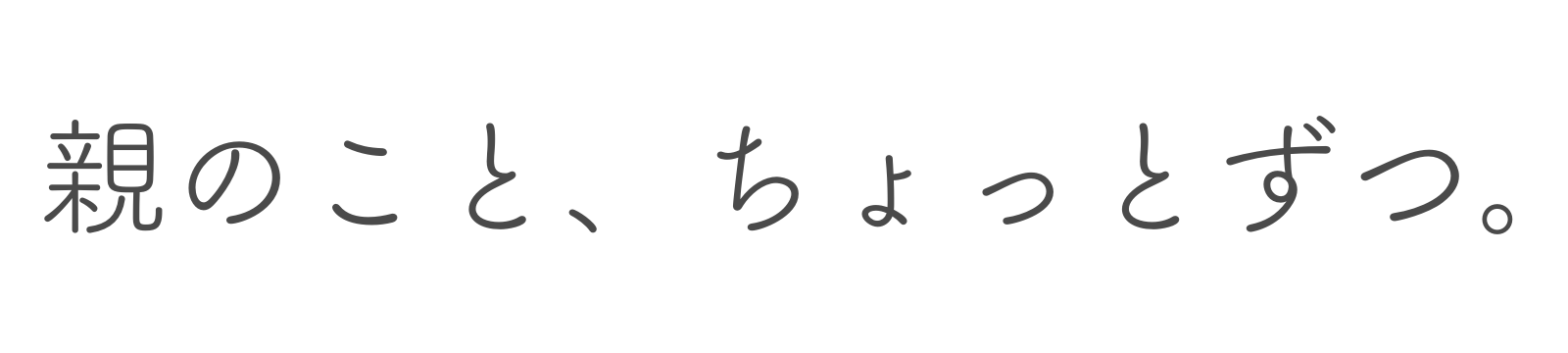
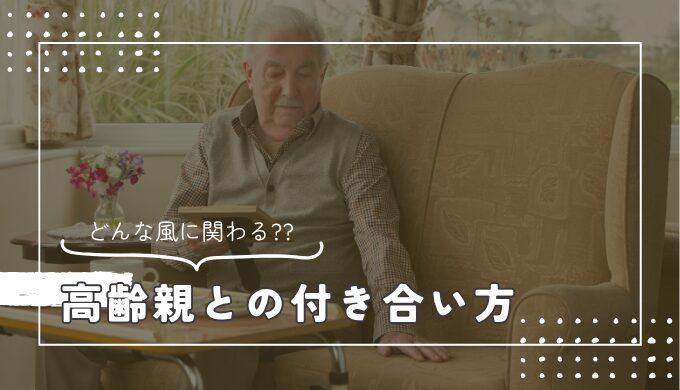

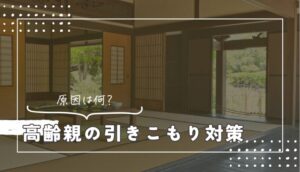

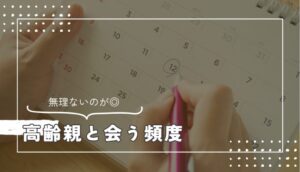
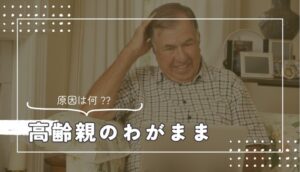
コメント