 お悩み
お悩み高齢になった親が1人暮らしをしているけど心配……



見守りカメラの設置を提案したけど、嫌がられてしまった……
本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、高齢になった親が見守りカメラの設置を嫌がるときの対処法を解説します。
- 親が高齢者向け見守りカメラの設置を嫌がる理由・対処法
- 高齢者向け見守りカメラの選び方
高齢者向け見守りカメラは、家族が遠くからでも親の安全を確認できる便利なツールのひとつです。
子供たちからしたら「実家に設置して、安心したい」と考えるかもしれませんが、親によっては見守りカメラの設置を嫌がる場合もあります。
高齢者が見守りカメラを嫌がる理由は、監視されていると感じることや操作が難しいと感じることが主な要因です。
とはいえ、カメラには多くのメリットがあることは事実なので、メリットや設置の目的を根気よく伝えて、親御さんにも納得してもらうことをおすすめします。
本記事では、高齢になった親が見守りカメラの設置を嫌がる理由や対処法を詳しく解説していきます。
おすすめの高齢者向け見守りカメラについては、下記の記事で詳しく紹介しているのでよろしければ併せてお読みください。
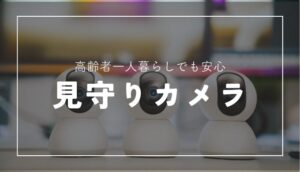
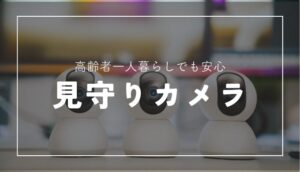
親が高齢者向け見守りカメラの設置を嫌がる理由
高齢者向けの見守りカメラは、遠方に住む家族が親の生活を安心して見守るための有効な手段のひとつです。
しかし、設置される側にとっては「生活を監視されているようだ」「まだそんなものは必要ない」と感じることもあるでしょう。
高齢になった親が見守りカメラの設置を嫌がる理由は、主に下記の通りです。
- 監視されていると感じる
- まだ必要ないと感じる
- 操作・設置が難しく使いこなせないと感じる
- 費用がかかってもったいないと感じる
- 録画データが流出したらどうしようと不安である
それぞれ詳しく解説していきます。
監視されていると感じる
高齢になった親が見守りカメラの設置を嫌がる理由のひとつは、カメラの設置により「生活を監視されている」と感じてしまうことではないでしょうか。
特に、一人暮らしや夫婦のみで暮らしている期間が長いと、カメラが設置されることへの拒否感が強まる場合もあります。
対処法としては、見守りカメラの設置は「プライバシーの監視」ではなく、あくまでも生活の安全を守るためのものと伝えることなどがあげられます。



特に、転倒や急病などの緊急時でも、離れた家族がすぐに気付けると強調すると良いでしょう。
また、見守りカメラの種類や設置位置についても相談し、納得してもらうことが重要です。
まだ必要ないと感じる
高齢者の中には「見守りカメラなんて、自分にはまだ必要ない」と感じる方もいます。
これまで健康に問題がなく、自立できている場合、特にそう感じる方もいるでしょう。
しかし、子供たちからしてみれば「元気じゃなくなってから、カメラを設置するのでは遅い」と考えるはずです。
見守りカメラを設置する際には、このような認識のずれを正す必要がありますが、あくまでも高齢になった親の意見を聞きつつ、見守りカメラを設置するメリットを伝えると良いでしょう。



会話機能付きのカメラであれば、子供や孫とも話しやすくなるなどと伝えてみても良いですね
操作・設置が難しく使いこなせないと感じる
高齢者が見守りカメラを嫌がる理由として、操作が難しいと感じる場合があります。
スマホの操作やカメラ、家電の操作などに不慣れな場合、カメラの設置や設定をおっくうに感じることもあるでしょう。
私の義祖母も「カメラを設置しても、壊れたらどうすればよいかわからないよ」と言い、カメラの設置に消極的でした。
とはいえ、見守りカメラは一度設置すれば、基本的に細かい操作は必要ないものも多くあります。



「普段の操作は必要ないよ」「壊れたり不安なことがあったりしたら、すぐに見に行くよ」と伝えるのが良いでしょう
費用がかかってもったいないと感じる
高齢者の中には「お金がかかる」と感じることに敏感になり、見守りカメラの設置をためらう方もいます。
私の母親も、割とこのタイプで、子供や孫にはお小遣いをくれるものの、自分に対してお金を使うことは嫌がります。
特に、年金暮らしで生活している場合や、配偶者に先立たれ一人暮らしをしている場合、費用がかかることに不安を覚える方もいるのではないでしょうか。
対処法としては、見守りカメラを母の日や父の日、誕生日プレゼントにしてしまうことです。



「私たちが安心するためだから、費用を出させて」と言って、カメラの費用負担は子供世帯持ちにするのもおすすめです
録画データが流出したらどうしようと不安である
高齢になった親が見守りカメラの設置を嫌がる理由のひとつに、録画データの流出リスクがあります。
見守りカメラや録画データの保存方法の仕組みを理解できないと、「遠くに離れたあなたたちだけでなく、色々な人がデータを見るんじゃないの?!」と不安になるケースもあるでしょう。
高齢者世代の中には、インターネットやSNSをあまり使っていない方も多く、個人情報の漏洩について強い不安感を持っている方もいます。
対処法としては、高齢になった親でもわかるように見守りカメラの仕組みや録画データの取り扱いについて確認しておくことが大切です。
基本的に、見守りカメラはセキュリティ面でも配慮されており、登録された方以外がデータを見ることはできません。
また、録画データをクラウドなどで保管する場合、信頼性の高いサービスを選ぶことが大切です。



私の母は「いつまでもデータを保管しないで!」と言うので、見守りカメラのデータは別のクラウドなどに移さないようにしています
高齢者向け見守りカメラの設置を嫌がるときの7つの説得方法
高齢者向け見守りカメラの設置を嫌がられたときには、下記などの方法で親を説得してみましょう。
- 親の健康・生活のためではなく防犯目的で設置すると伝える
- 子供からではなく孫や友人・知人から勧めてもらう
- 同じように見守りカメラを利用している方の体験談を読んでもらう
- まずはレンタルで試して録画映像を確認してもらう
- プライバシーを守れる設置場所を考える
- 「私が安心できる」と伝える
- 強制しすぎない
それぞれ詳しく解説していきます。
親の健康・生活のためではなく防犯目的で設置すると伝える
「自分はまだ元気だから必要ない」と感じている高齢者に見守りカメラの設置を納得してもらうには、健康・生活のためというより、防犯目的で設置したいと伝えてみましょう。
近年、一人暮らしの高齢者を狙った強盗も増えており、防犯対策をしたいと考える高齢者も多くいるからです。
健康・生活のためと言われると「自分のせい」「自分が年老いてきたからだ」と感じてしまう方もいますが、防犯対策の一環であれば、外部要因による理由と思ってもらえる可能性もあります。
子供からではなく孫や友人・知人から勧めてもらう
子供が高齢になった親に見守りカメラの設置を勧めると、お互い距離が近すぎる分、「そんなものは必要ない」と拒まれてしまう恐れもあります。
このような場合、子供ではなく、孫や友人・知人から見守りカメラを勧めてもらうのも良いでしょう。
孫や友人・知人から勧めてもらうと、親自身が「他の人も勧めているなら」と受け入れやすくなるからです。



第三者の意見を取り入れることで、親にとっては「説得された」という感覚が薄れ、自然に導入を受け入れやすくなるでしょう
同じように見守りカメラを利用している方の体験談を読んでもらう
他の高齢者が実際に見守りカメラを導入している例を紹介することも、説得の有効な手段のひとつです。
「思っていたよりも便利だった」「家族との連絡がスムーズになった」など、実際の利用者の声を読むことで、見守りカメラに対する抵抗感が減る場合もあるでしょう。



親が共感できるような具体的な事例を紹介し、導入後のメリットを伝えることが説得に繋がるはずです
まずはレンタルで試して録画映像を確認してもらう
親が見守りカメラの導入に不安を感じている場合、「まずは試してみる」という方法も有効です。
まずは、レンタルでカメラを借りてみて、実際に設置した後の様子や録画映像を確認してもらいましょう。
親が自分で録画データを確認し、カメラの必要性や安心感を実感できれば、納得して導入を受け入れる可能性が高くなります。



レンタルということで購入よりも、ハードルが低いと感じてもらえるはずです
プライバシーを守れる設置場所を考える
安全のためといっても、見守りカメラ=プライバシーの侵害と考える高齢者もいます。
「監視されている」と感じることを避けるために、親子で納得できる場所にカメラを設置しましょう。
具体的には、寝室などといったプライベートな空間にはカメラを設置するのを避け、リビングや玄関などに設置することをおすすめします。
加えて、画角が広いカメラを設置することで、部屋の隅に置いても部屋全体を撮影できるので、親が普段の生活でカメラを意識せずにすみます。
「私が安心できる」と伝える
高齢者向けの見守りカメラの設置を進める際、「私が安心できる」という気持ちを親に伝えると良いでしょう。
親自身が安心して生活するためというより、子供が安心できるために設置するという視点で話すと、親は「子供たちのためなら」と受け入れやすくなります。



特に、実家と遠方の場合、効果的な伝え方となるはずです
強制しすぎない
最も重要なのは、親に見守りカメラの設置を強制しすぎないことです。
無理に設置を勧めると、親の反発を招き、逆にカメラの設置を拒否される可能性があるからです。



場合によっては、見守りカメラの導入にすぐは納得してくれないこともあるでしょう
その場合でも、時間を掛けて少しずつ、親にカメラのメリットを伝え、見守り体制を整えていくと良いでしょう。
高齢者向け見守りカメラの選び方
高齢者向け見守りカメラはいくつかあるため、下記などの基準で選ぶことをおすすめします。
- 動体検知機能や温度センサーがついているか
- 夜間撮影できるか
- 部屋全体を撮影できるか
- 通話機能はついているか
- 見た目に圧迫感がないか
それぞれ詳しく解説していきます。
動体検知機能や温度センサーがついているか
見守りカメラを購入する際には、動体検知機能や温度センサーの有無を確認しておきましょう。
| 機能の種類 | 概要 |
|---|---|
| 動体検知機能 | カメラが周囲の動きを感知するとアラートを送る機能 |
| 温度センサー | 温度変化を感知する機能 |
動体検知機能があれば、高齢者が自宅で転倒した際や急病の際に気付きやすくなります。
また、温度センサーも高齢者の体調不良や熱中症などに気付ける可能性が上がります。
カメまるM温度計という見守りカメラは温度センサーが付いており、熱中症対策にもおすすめです。
夜間撮影できるか
高齢者の自宅に見守りカメラを設置するのであれば、昼間だけでなく夜間撮影できるもの(赤外線機能付き)を選ぶと安心です。



夜間撮影もしたいのであれば、赤外線撮影がついているものを選びましょう
また、玄関などに夜間撮影機能付きのカメラを設置することで、一人暮らしの高齢者世帯の防犯対策にもつながります。
部屋全体を撮影できるか
見守りカメラを設置する際には、親が過ごす部屋全体をカバーできるカメラを選ぶことをおすすめします。
水平画角120度以上のものを選べば、部屋の隅に置いても、部屋全体を撮影しやすくなります。



「カメラを設置しているという圧迫感を減らせる」のもメリットといえるでしょう
通話機能はついているか
高齢になった親の見守りだけでなく、コミュニケーションも重視したいのであれば、通話機能付きのものを選ぶのもおすすめです。
通話機能付きの見守りカメラであれば、遠隔地に住んでいる家族でも会話できるようになります。



親がスマホやパソコンを使いこなせない場合、カメラを導入して通話するのも良いですね
ELEPROが販売しているV3という見守りカメラは、カメラ本体に画面が付いており、単体でビデオ通話を行えます。
見た目に圧迫感がないか
見守りカメラは、日常的に過ごす空間に設置するため、見た目にもある程度こだわることをおすすめします。
例えば、防犯目的で玄関ドアに付けるようないわゆる監視カメラといった物を選ぶと、親がストレスを感じる場合もあるからです。
可能であれば、デザインがシンプルで大きすぎないものを選ぶと良いでしょう。
Ring Indoor Cam第二世代は、2023年のグッドデザイン賞を受賞しており、最新家電のような見た目の見守りカメラです。



インテリアにこだわりがある親におすすめしたい見守りカメラのひとつです
親が高齢者向け見守りカメラの設置を嫌がるときによくある質問
最後に、親が高齢者向け見守りカメラを設置する際によくある質問について、回答と共に紹介していきます。
- 高齢者向け見守りカメラを設置するメリットとは何ですか?
-
高齢者向け見守りカメラを設置するメリットは、遠隔地に住む家族が親の安全を確認できることです。
カメラを通じて、転倒や急病などの緊急事態に迅速に対応でき、早期に手を打つことができる可能性もあるでしょう。
- 高齢者向け見守りカメラを設置するデメリットとは何ですか?
-
高齢者向け見守りカメラを設置するデメリットは、プライバシーの問題などがあります。
親が「監視されている」と感じて、拒否感を示すこともあるでしょう。
さらに、カメラの設置や維持費用がかかることもデメリットとしてあげられます。
- 高齢者向け見守りカメラの購入には介護保険を適用できますか?
-
高齢者向け見守りカメラの購入には、原則として介護保険は適用されません。
介護保険は、介護が必要な高齢者のために提供されるサービスや機器に限定されているからです。
- 高齢者が抵抗を感じない見守りカメラの設置場所はどこですか?
-
高齢者が抵抗を感じにくい見守りカメラの設置場所は、玄関やリビングなど「生活動線の一部」として自然に置ける場所です。
寝室や浴室などプライベート空間を避け、会話や生活の様子を確認できる範囲にすることで安心感を保てます。
【まとめ】伝え方やカメラ選びを工夫すれば親も納得しやすくなります
高齢になった親が見守りカメラの設置を嫌がる理由としては、監視されている気分になるというものや、設置費用がかかるなどのものがあげられます。
見守りカメラの仕組みやデータの保存方法などについて詳しくなく、やみくもに反対している可能性もあるので、設置するメリットや目的について伝えることで納得してもらいやすくなります。
高齢者向け見守りカメラを選ぶ際には、動体検知機能や夜間撮影機能、広角の画角など、親の生活環境に合った機能を重視することも大切です。
本ブログでは、シニア世代に突入する親といつまでも元気に楽しく生活するために関する情報を発信していきます。



ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
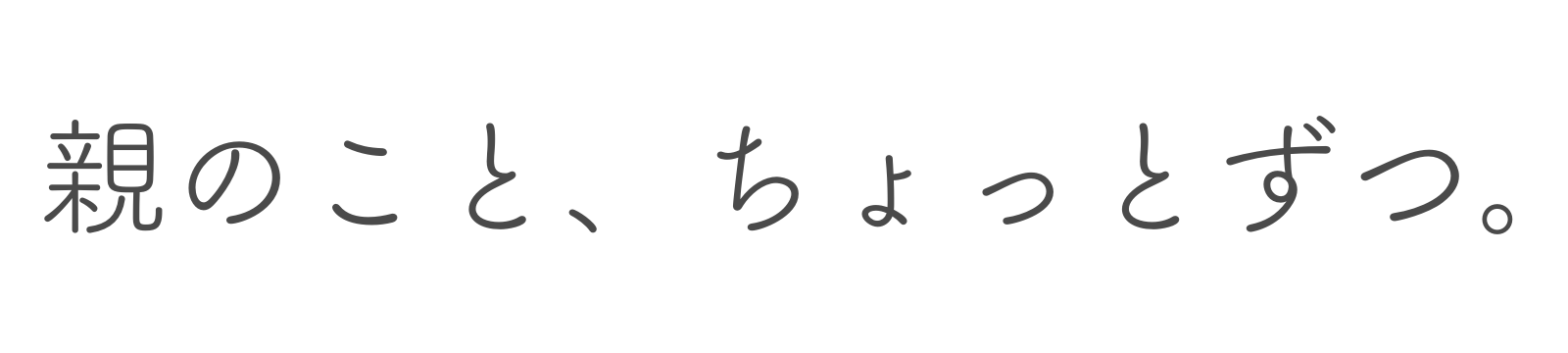






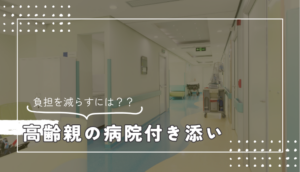
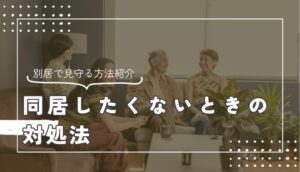
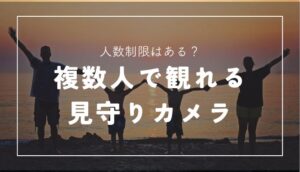

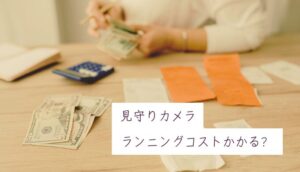
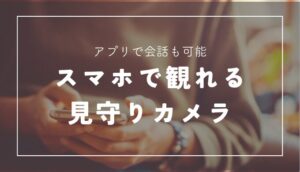
コメント