 お悩み
お悩み実家の親が料理をしなくなり、惣菜ばかり食べているみたい……



栄養も偏るし、このままどんどん家事をしなくなり認知症になったらどうしよう……
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、高齢者が料理をしなくなる理由やリスク、対処法を解説します。
- 高齢者が料理をしなくなる理由
- 高齢者が料理をしなくなるのは認知症の兆候なのか
- 高齢者が料理をしなくなることによる健康リスク
- 高齢者が料理をしなくなったときにできる5つのサポート
高齢になると、これまで当たり前にできていた料理をしなくなる方が少なくありません。
高齢者が料理をしなくなる原因としては、体力や気力の低下、視力や手先の衰え、一人暮らしでの「作る楽しみ」の減少など様々なものが考えられます。
場合によっては、認知症の初期症状として料理の段取りや味付けが難しくなる場合もあるので、高齢になった親が料理をしない場合には他の様子も気にかけておきましょう。
また、料理をしなくなり惣菜やコンビニ弁当などに頼るようになると健康リスクもあるのでご注意ください。
料理の負担が大きければ、宅配弁当や宅食サービスの利用も検討しましょう。
本記事では、高齢者が料理をしなくなる理由や健康リスク、家族がサポートする方法を解説します。
高齢者が料理をしなくなる理由
高齢になると体力や気力が衰え、料理などの家事が負担になる場合もあります。
高齢者が料理をしなくなる理由は、主に以下の通りです。
- 体力や気力の低下によるもの
- 視力・手先の衰えで調理が難しくなる
- 一人暮らしで「作る楽しみ」がなくなる
- 買い物や片付けが負担になっている
それぞれ詳しく解説していきます。
体力や気力の低下によるもの
高齢になると、若い頃に比べて体力が落ち、長時間立って調理をすることが負担に感じられるようになります。
加えて、加齢に伴い気力も低下し「今日は面倒だから作らなくてもいいか」と感じる機会が増えるのも自然なことです。



特に、持病を抱えていたり、体調の波がある場合には、料理が大きな負担となるはずです
自炊を避けた結果、食事が簡単に済ませられるパンやお菓子、インスタント食品に偏ってしまうことも少なくありません。
視力・手先の衰えで調理が難しくなる
料理は細かい作業が多いため、視力や手先の機能が衰えてくると負担も大きくなりますし、危険も増えます。
例えば、包丁を扱う際に手元が見えづらかったり、野菜の皮むきで指を切りそうになったりする経験が重なると、料理はやめておこうという気持ちに傾くはずです。
また、加齢による手の震えや関節の痛みも、調理を妨げる要因となります。



現役世代では想像しにくい身体の衰えが積み重なり、料理が大きな負担となってしまうのです
一人暮らしで「作る楽しみ」がなくなる
自分で食べるためだけに料理をすることは、心理的な負担も大きくなります。
料理は「誰かと一緒に食べるからこそ楽しめる」という側面も大きいものです。



主婦の方で夫も子供もいない日は、手抜きご飯や惣菜を楽しむ方も多いですよね
自分一人のために料理をするのは面倒と感じる方もいますし、一人分だけを調理すると食材が余りやすく、結果的に割高になってしまうこともあります。
そのため「買った方が安くて楽」と判断し、コンビニやスーパーのお惣菜で済ませるようになるケースも多く見られます。
買い物や片付けが負担になっている
料理には、調理だけでなく買い物や片付けといった一連の作業が伴います。
重い食材を持ち帰るのは体力的に大変であり、シンクにたまった食器を洗うことやゴミを処理することも面倒に感じやすくなります。
特に腰や膝の不調を抱える高齢者にとっては、これらの作業が大きな負担となるはずです。
そのため「作って片付けるくらいなら、初めから買ってしまおう」という思考に切り替わりやすく、結果的に料理をしなくなる生活リズムへと移行していく方もいます。
高齢者が料理をしなくなるのは認知症の兆候?
離れて住む親が最近料理をしておらず、惣菜やコンビニ弁当ばかり食べるようになったと聞くと、認知症ではないだろうかと不安になる方もいるかもしれません。
確かに、料理を億劫に感じたり失敗が増えたりするのは、認知症の初期症状として見られることがあります。
しかし、認知症の症状以外でも料理をしなくなることはあるので、生活全体を見て認知症の兆候があるかを判断することが大切です。
本章では、高齢者が料理をしなくなるのは認知症の兆候なのか、詳しく解説していきます。
認知症の初期に見られる「段取り力」の低下
高齢者が料理をしなくなるのは、認知症の初期症状のひとつである段取り力の低下が原因であることもあります。
料理は単に食材を切ったり炒めたりするだけでなく、①冷蔵庫から必要な食材を取り出す、②下ごしらえをする、③火加減を調整するといった複数の工程を組み立て、順序よく実行しなければなりません。
このような段取り力は、脳の前頭葉の働きに関係しており、認知症の初期症状として低下しやすい部分のひとつです。
そのため、今までは普通に作れていた味噌汁を前にして、具材を入れ忘れたり鍋を火にかけっぱなしにしてしまったりする場合には、認知症のサインとして現れている可能性があります。
味付けの変化や料理を忘れる行動との関連
料理の味付けにも、認知症の兆候が現れることがあります。
これまで適度に調味料を使っていた人が、急に塩辛くしたり、逆に味がほとんどしない料理を作ったりするようになるケースです。
味覚そのものが変化することもありますが、多くは「どの調味料をどれくらい入れるか」という記憶や判断力の低下が原因となっています。
加えて、調理していたことそのものを忘れてしまい、鍋を火にかけたまま外出したり食材を冷蔵庫に入れ忘れて腐らせてしまったりといった行動が見られる場合には、特に注意しなければなりません。
認知症以外の病気や要因でも料理をやめることはある
ここまで料理をしなくなることや料理に失敗することと認知症との関係について解説してきました。
ただし、料理をしなくなった=必ず認知症というわけではありません。
体力や視力の低下、うつ病など、他の要因によって料理をやめる高齢者も多くいるからです。
例えば、うつ病の場合には「何もやる気が起きない」という状態から料理を放棄するケースがありますし、糖尿病や高血圧の治療によって味覚が変わり、調理そのものが楽しめなくなることもあるでしょう。
そのため、料理をしなくなった=認知症と考えるのではなく、原因を見極め適切に対処していくことが大切です。
高齢者が料理をしなくなることによる健康リスク
高齢になると料理が負担になるものの、そのまま自炊をせず惣菜やコンビニ弁当、外食などに頼り続けると、以下のような健康リスクが生じる恐れがあります。
- 低栄養・フレイルの進行
- インスタント食品や菓子パン中心による生活習慣病リスク
- 食事リズムの乱れによる体調不良
- 社会的孤立やうつの進行につながる可能性
それぞれ詳しく解説していきます。
低栄養・フレイルの進行
料理をしなくなると、栄養バランスのとれた食事を準備することが難しくなります。
特に、高齢者は筋肉量が減少しやすく、たんぱく質やビタミン、ミネラルが不足すると低栄養状態に陥る可能性があるので注意しなければなりません。
低栄養はフレイル(加齢に伴う心身の虚弱)の進行を早め、転倒や寝たきりにつながる恐れがあります。



惣菜やコンビニ弁当ではたんぱく質やビタミンが不足しがちで、炭水化物が多めになってしまうので注意しましょう
インスタント食品や菓子パン中心による生活習慣病リスク
高齢者が料理をやめると、手軽に入手できるインスタント食品や菓子パン、総菜に頼るケースが増えます。
しかし、これらは高塩分・高脂肪であり、糖分も多い傾向があります。
たまに食べる分には問題ないことが多いですが、長期間こうした食事が続くと、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病のリスクが高まります。



特に、高齢者は若い世代に比べて代謝が落ちているため、同じ食事内容でも体への負担が大きくなりがちです
食事リズムの乱れによる体調不良
料理をしない生活が続くと、食事の時間が不規則になりやすくなります。
例えば、「お腹が空いたらパンをつまむ」「夕食を抜いてお菓子で済ませる」といった生活が習慣化すると、血糖値の変動が大きくなり、倦怠感や集中力低下を招きます。
また、夜遅くに食事をとる習慣は胃腸に負担をかけ、睡眠の質を下げる要因にもなります。



栄養面だけでなく、食事の時間もバラバラになりやすくなるので注意しなければなりません


社会的孤立やうつの進行につながる可能性
料理は、自分や家族のために作るという生活の張り合いにもなり、料理をしなくなることは心理的にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
特に、一人暮らしの高齢者は、料理をしなくなることで人と食事を共にする機会が減少し、孤食が進行します。
高齢者が料理をしなくなったときにできる5つのサポート
心身の衰えにより調理が負担になり、高齢者が料理をしなくなったときには、無理のない範囲で家族が以下のようなサポートをすると良いでしょう。
- 宅配弁当・宅食サービスを取り入れる
- 買い物・調理を家族が部分的にサポートする
- 火を使わない調理法や簡単レシピを取り入れる
- 一緒に食べる機会を増やして食事の楽しみを取り戻す
- 見守りサービスや生活支援サービスを活用する
それぞれ詳しく解説していきます。
宅配弁当・宅食サービスを取り入れる
自炊をやめても栄養バランスのとれた食事を食べられるように、宅配弁当や宅食サービスの利用を検討しても良いでしょう。
近年では、高齢者向けの宅食サービスも増えてきており、消化にやさしいやわらかめのメニューやカロリーや塩分量を制限しているメニューを提供してくれるところもあります。
宅食サービスときくと、毎日決まったメニューが届く味気ない印象がありますが、最近では自分でメニューを選べる冷凍タイプのお弁当も増えつつあります。



冷凍タイプならまとめ買いしておき、必要なときに食べることが可能です
買い物・調理を家族が部分的にサポートする
高齢者が料理を完全にやめてしまう前に、家族が部分的にサポートするのも有効です。
例えば、食材の買い物が負担になっているのであれば、食材の買い物だけ家族が手伝うのも良いでしょう。



他にも、おかずを一品だけ作って実家に持っていったり、下ごしらえを一緒にしたりするのもおすすめです
火を使わない調理法や簡単レシピを取り入れる
親が高齢になり包丁やガスコンロの扱いに不安を感じている場合には、包丁や火を使わずに作れるレシピを提案するのもおすすめです。
昔は料理をする際に包丁や火を使うことは当たり前でしたが、近年では冷凍野菜やカット野菜など便利なものも増えています。
調理器具についても、電子レンジや電気調理鍋など火の危険性が少ないものもたくさんあります。



高齢になると新しいものを取り入れることが難しくなるため、子供や孫が提案してみると良いでしょう
一緒に食べる機会を増やして食事の楽しみを取り戻す
「自分しか食べないのに料理しても仕方ない」と考えてしまい、料理をしなくなった場合には、家族や友人と食卓を囲んだり、地域の食事会やイベントに参加したりするのも良いでしょう。



食事は単なる栄養補給ではなく、会話や交流の場でもあります
人と一緒に食べる時間を持つことで「また誰かと食べたい」という意欲が芽生え、料理や食事に対するモチベーションも自然と高まります。
見守りサービスや生活支援サービスを活用する
高齢者が料理をやめる背景には、体力や認知機能の低下が隠れている場合もあります。
高齢になった親の変化にすぐ気付くために、見守りサービスや生活支援サービスの利用も検討しましょう。
例えば、見守りカメラを設置すれば「食事をとっているか」「調理の様子に変化がないか」などを離れていても確認できます。
また、地域の生活支援サービスを利用すれば、買い物代行や家事援助が提供されており、日常生活の負担を大きく減らせるでしょう。


高齢者におすすめの宅食サービス
高齢になり料理が難しくなってきた場合には、高齢者向けの宅食サービスを利用するのもおすすめです。
宅食サービスにはいくつかありますが、特におすすめのものは下記の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
ワタミの宅食ダイレクト
- 管理栄養士が設計した栄養バランスのよい冷凍惣菜を食べられる
- 対応エリアは全国各地(一部離島を除く)
- 電子レンジで温めるだけでいつでも好きな時間に食べられる
- 塩分やカロリーに配慮したラインナップで健康管理がしやすい
- 定期購入だけでなく都度注文も可能でライフスタイルに合わせやすい
- まとめ買いで冷凍保存できるため、食事時間が不規則な高齢者でも利用しやすい
ワタミの宅食ダイレクトは冷凍弁当として届くため、自分の好きなタイミングで温めて食べられる点が大きな魅力です。



電子レンジで簡単に解凍できるので、火を使わずに済む点も安心です
市販の惣菜やコンビニ弁当だと、どうしても添加物や栄養バランスが気になる方も多いですが、その点ワタミの宅食ダイレクトは管理栄養士が監修しているため、栄養やカロリー面でも信頼できます。
惣菜の種類も100種類以上あり、毎日違うメニューを楽しみたい方や同じものばかりでは飽きてしまう方にもぴったりです。
私や母も経験したことがあるのですが、宅配弁当や宅食サービスは注文時に食べたいと思っていてもいざ届くと気分が変わっており食べる気がなくなるということがちょくちょくあります。
しかし、ワタミの宅食ダイレクトは種類が豊富ですし、冷凍保存が可能なので、一度にまとめて注文しておき、その日の気分で選んで食べられます。



偏食気味でスーパーなどの惣菜が苦手な父も、いくつかのメニューは好んで食べてくれています
メディミール
- 管理栄養士と医療チームが監修し、健康面に配慮した冷凍弁当を提供
- カロリー・塩分を控えたい、糖尿病や腎臓病など特殊な制限食に対応
- 電子レンジで温めるだけの簡単調理
- メニューは150種類以上、飽きずに楽しめる豊富なバリエーション
- 無添加・国産食材へのこだわりと、やわらか食・刻み食にも対応
メディミールは、管理栄養士や医療専門チームが監修したメニューを提供する宅配サービスです。
高齢の方や、糖尿病・高血圧といった持病を持つ方の栄養管理をサポートしてくれるのが大きな特徴です。



食事のカロリーや塩分にも細かく配慮されており、宅食でありながら健康維持に役立てやすい点も安心できます
糖尿病や高血圧などの制限食は、家庭で作ろうとするとどうしてもレパートリーが限られてしまい、似たような献立になりがちです。
その点、メディミールは150種類以上のメニューを用意しているため、毎日違う食事を楽しめます。



計算すると、1日3食×30日食べても同じメニューが被らないほどの豊富さです
また、メディミールの強みは監修だけにとどまりません。
献立作成や商品開発、調理、さらには栄養相談まで、すべての工程に管理栄養士が関わっています。
さらに、お客様対応も管理栄養士が行っているため、万が一わからないことや不安があった際にも専門的なアドバイスを受けられる点は心強いです。
健康直球便
- 管理栄養士監修で、糖質・カロリー・塩分・たんぱく質などさまざまな制限食に対応
- 主菜1品+副菜3品のセットで満足感が高く、バラエティ豊かなラインナップ
- 冷凍で長期間保存可能
- 噛む力・飲み込む力が弱くなった高齢者向けの「やわらか食」「ムース食」も充実
- 1食500円程度から利用でき、割安でコスパが高い宅食サービス
健康直球便は、管理栄養士が監修した栄養バランスのとれた冷凍弁当を届けてくれる宅配サービスです。
制限食の種類が豊富で、高齢の方でも利用しやすいメニューが揃っている点が特徴です。
高齢者向けの制限食が豊富であり、メニューも以下のように多岐にわたります。
- 糖質・カロリー調整食
- カロリー・塩分調整食
- 塩分・たんぱく調整食
- 消化にやさしい食
- やわらか食
- ムース食
いずれも冷凍で届くため長期保存が可能で、食べたいときに電子レンジで温めるだけで手軽に楽しめます。
各コースは主菜と副菜のセットになっており、栄養バランスはもちろん、ボリュームや味のバリエーションにも工夫がされています。
「柔らかいものや消化の良いものを食べたいけれど、自分で作るのは大変」「制限食だと献立がワンパターンになりがち」という悩みを抱える方にぴったりです。
また、健康直球便は高齢者向けに特化したサービスなので、一人暮らしの方だけでなく、家族と同居しているけれど健康状態に合わせた別メニューを取り入れたい方にも向いています。



料理の負担を減らしながら、安心しておいしい食事を続けたい方におすすめの宅食サービスといえるでしょう
高齢者の料理についてよくある質問
最後に、高齢者の料理についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 料理ができなくなるのは認知症症状のひとつですか?
-
料理が難しくなることは、認知症の初期症状として見られるケースがあります。
料理には、献立を考えたり、必要な食材を揃えたりといった段取り力や記憶力も求められるからです。
認知症になると、これらの認知機能が失われていくため、これまで問題なくこなせていた料理ができなくなることもあります。
- 高齢者の食が細くなる理由は何ですか?
-
高齢者の食が細くなるのは加齢による自然な変化であり、病気ではないケースも多々あります。
まず、高齢者は基礎代謝や筋肉量が低下するため、若い頃よりもエネルギーを必要としなくなり、食欲自体が落ちやすくなります。
さらに、歯や入れ歯のトラブル、嚥下機能の低下によって「噛みにくい」「飲み込みにくい」と感じると、無意識に食事量を減らしてしまいます。
【まとめ】料理が負担になったら宅食サービスを上手に活用しましょう
高齢者が料理をしなくなる背景には、身体的な衰えや心理的な要因、さらには認知症などの病気が関わっている場合もあります。
放置してしまうと、栄養不足や生活習慣病、孤立感の増大など、心身に大きな影響を与える可能性があるので注意しなければなりません。
料理の負担が大きい場合には、宅食サービスの利用や家族による部分的なサポートなども行っていくと良いでしょう。
本ブログで紹介したおすすめの宅配弁当や宅食サービスは、下記の通りです。
このブログでは、高齢になった親を見守るサービスやアイデアを紹介しています。



ここまで読んでいただき、ありがとうございました
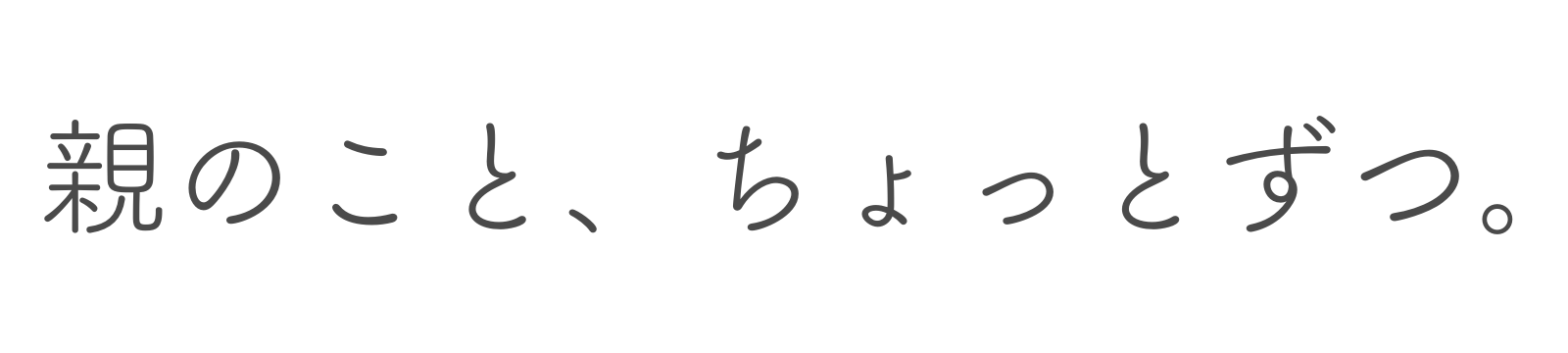



コメント