 お悩み
お悩み実家に住む親の食事時間が結構バラバラらしい……



この前、夕方に電話したらまだ何も食べていないって言ってた……心配
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、高齢者の食事時間がバラバラになりやすい理由や対処法を解説します。
- 高齢者の食事時間がバラバラになりやすい理由
- 高齢者の食事時間がバラバラになるのは認知症の兆候なのか
- 高齢者の食事時間がバラバラになることによる健康リスク
- 高齢者の食事時間を規則正しくするコツ
高齢になり、食事時間がバラバラになることは決して珍しいことではありません。
加齢に伴い、体内時計のバランスが崩れ、朝食を抜いてしまったり、夜遅くに軽く食べる習慣がついたりすることもあります。
しかし、家族にとっては「食生活が不規則にならないか」「栄養は摂れているだろうか」と心配になることもあるでしょう。
高齢になった親の食事時間が気になるのであれば、調理の負担を軽減するために宅食サービスを利用したり、ビデオ通話などを利用して食事中にコミュニケーションを取るなどの工夫をするのもおすすめです。
本記事では、高齢者の食事時間が不規則になる理由や健康リスク、対処法について詳しく解説します。


高齢者の食事時間がバラバラになりやすい理由
高齢者の食事時間がバラバラになりやすい理由はいくつかあり、主に下記の通りです。
- 加齢による生活リズムの乱れ
- 一人暮らしによる孤食・気ままな食習慣
- 体調や服薬スケジュールの影響
- 歯や消化機能の低下により食べたい時間がばらつく
それぞれ詳しく解説していきます。
加齢による生活リズムの乱れ
高齢になると、体内時計を司る脳の働きが弱まり、睡眠や覚醒のリズムが不安定になりやすくなります。
昼夜逆転や昼寝が長くなることも多く、その結果、お腹が空く時間もバラバラになりやすくなります。



仕事をしていたり育児をしていたりすると、どうしても早起きしなければならず、食事のリズムが安定しますが、高齢の方はそれも難しいですよね
さらに、夜間頻尿などで睡眠が分断されると、朝食を抜いてしまったり、夜中に軽食をとる習慣がついたりすることもあります。
一人暮らしによる孤食・気ままな食習慣
高齢になり一人暮らしとなると、家族の生活リズムに合わせる必要がなくなり、食事の時間もバラバラになりやすくなります。
お腹が空いたときに食べたり、面倒に感じて食事を抜いたりするなど、自分の気分や体調に合わせた食習慣になりがちです。
また、食事は栄養補給だけでなく、コミュニケーションの方法となる場合もあります。
そのため、一人暮らしをしており、誰かと食べる楽しみが減ると、簡単なパンや菓子類で済ませてしまうことも増え、食事時間や内容が不規則になりやすい傾向があるため注意しなければなりません。
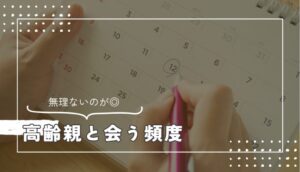
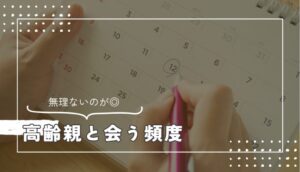
体調や服薬スケジュールの影響
高齢になると持病を抱えている方も多く、服薬のタイミングに合わせて食事を調整する必要が出てきます。



薬によっては「食前」「食後」「空腹時」など細かい指定があるため、普段の食事リズムが薬に引っ張られてしまうのです
また、体調の波によって食欲がわかない時間帯があると、その後にまとめて食べたり、夜遅くに食事を取ったりすることもあります。
歯や消化機能の低下により食べたい時間がばらつく
加齢によって歯や歯茎が弱くなり、咀嚼力が低下すると硬いものは避けたいと感じるだけでなく、食事に時間がかかるようになります。
また、胃腸の働きが弱くなると、一度にたくさん食べられなくなり、結果的に少しずつ複数回に分けて食べるというスタイルになることも珍しくありません。



このような状況では、従来の朝昼晩といった決まった時間に食べる習慣から外れやすくなり、自然と食事の時間が不規則になってしまいます
高齢者の食事時間がバラバラになるのは認知症の兆候?
高齢になった親の食事時間が不規則になったとき、認知症の初期症状ではないかと心配する方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、食事時間が不規則になることだけでは認知症の兆候とは言えず、他の様子とあわせて判断する必要があります。
本章では、高齢者の食事時間がバラバラになるのは認知症の兆候なのか解説していきます。
生活リズムの乱れは認知症の初期症状のひとつである
認知症の初期症状では、脳の働きの低下によって昼夜の区別がつきにくくなることがあります。
これにより、日中に眠ってしまい夜型生活になった結果、食事の時間が不規則になるケースもあります。



生活リズムの崩れが加齢や一人暮らしによるものなのか、認知症の症状なのか見極めなければなりません
食事を忘れたり繰り返したりすることも認知症の初期症状のひとつである
認知症の初期段階では「食事をとったかどうかを思い出せない」といった記憶障害が見られることがあります。
その結果、食事を抜いてしまったり、逆に短時間のうちに再び食べてしまったりすることがあります。
本人は、「食べた記憶がない=食べていない」と思い込むことも多く、結果として食事時間が不規則になるのです。
冷蔵庫に同じものが複数入っていたり、調理途中のまま放置されていたりする状況は、認知症が疑われるので、必要に応じて医療機関を受診する必要があります。
認知症以外の要因で食事時間が乱れることもある
高齢者の食事時間が不規則になる場合、原因が認知症ではない場合もあります。
服薬や消化機能の低下などで食事の時間がばらつくことはありますし、精神的なストレスや季節の変わり目の体調不良によっても食欲や食事時間に変化が生じます。
食事時間のばらつきが見られた場合は、すぐに認知症だと決めつけるのではなく、生活全体を観察し、他の行動の変化と併せて判断することが大切です。
高齢者の食事時間がバラバラになることによる健康リスク
高齢になった親の食事時間が不規則になることは珍しくはないものの、長期的にその状態が続くと、以下のような健康リスクが生じる場合もあります。
- 低栄養やフレイル(虚弱)につながるリスク
- 血糖値や血圧のコントロールが難しくなる
- 服薬の効果が十分に得られなくなる
- 生活全体のリズム(睡眠・活動量)に悪影響を及ぼす
それぞれ詳しく解説していきます。
低栄養やフレイル(虚弱)につながるリスク
食事時間が不規則になると、必要な栄養素を十分に摂取できなくなるリスクが高まります。
例えば、朝食を抜いてしまうとタンパク質やビタミン、ミネラルの不足が生じやすくなりますし、夜遅くに軽食で済ませる習慣が続けば栄養バランスが偏りやすくなるからです。
栄養が偏った結果、筋力や体力が低下し、フレイル(虚弱)の状態に陥る可能性があります。



フレイルになると、転倒や骨折、感染症への抵抗力低下など、生活の質全体に悪影響が及ぶため注意しましょう
血糖値や血圧のコントロールが難しくなる
糖尿病や高血圧を抱える高齢者にとって、食事のタイミングは治療や健康維持に直結する要素です。
食事がばらばらになると、血糖値の変動が大きくなり、低血糖や高血糖のリスクが増してしまいます。
また、塩分や水分の摂取タイミングが不規則になることで血圧が安定しにくくなり、心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患につながる恐れもあるので注意しなければなりません。
服薬の効果が十分に得られなくなる
高齢者の多くは複数の薬を服用していますが、薬によっては「食前」「食後」など摂取のタイミングが細かく指定されています。
食事時間が乱れると薬を飲み忘れたり、逆に短い間隔で重複して服用してしまうなどのトラブルが発生しやすくなるので注意しなければなりません。



場合によっては、薬の効果が十分に発揮されなかったり、副作用のリスクが高まったりすることもあります
服薬管理は高齢者の健康維持に直結するため、食事とセットで習慣化できる環境を整えることが大切です。
生活全体のリズム(睡眠・活動量)に悪影響を及ぼす
食事は体内時計や生活リズムを整える大切な要素でもあり、不規則な時間に食べると眠りが浅くなったり、日中に強い眠気が出たりして活動量の低下につながります。



生活リズムの変化により食事の時間が不規則になると、どんどん悪循環に陥る恐れもあるのでご注意ください
高齢者の食事時間を規則正しくするコツ
高齢者の食事時間が不規則になりそうなときには、無理のない範囲で生活リズムを整え、規則正しく生活するようにしていきましょう。
具体的には、以下のような方法で食事の時間や生活リズムを整えることをおすすめします。
- 無理に時間を揃えず「おおまかなリズム」を意識する
- 家族や介護者と一緒に食べる機会をつくる
- 宅配弁当や宅食サービスを活用して食事を固定化する
- 見守りカメラやリマインダー機能で食事時間を可視化する
それぞれ詳しく解説していきます。
無理に時間を揃えず「おおまかなリズム」を意識する
高齢者の場合、体調や食欲に波がありますし、仕事や育児などで予定が詰まっているわけでもないので、若い頃のように毎日ぴったり7時に朝食といった生活は現実的ではありません。
むしろ、「朝は7〜9時の間に何か食べる」「昼は12〜13時頃」「夜は18〜20時までに食べ終える」といったおおまかなリズムを意識することが大切です。



1日の中で大きなズレが出ないように調整することで、本人の負担を減らしつつ、体内時計を整えやすくなります
家族や介護者と一緒に食べる機会をつくる
家族や支援者の協力が必要になりますが、できるだけ一人で食事を摂る機会を減らすのも有効です。
一人暮らしの高齢者にとって、孤食は食事リズムを乱す大きな要因となるからです。
誰かと一緒に食べる機会があるだけで、自然と決まった時間に食事をとる習慣が身につきます。
実家が離れていて物理的に一緒に食べることが難しい場合には、家族が電話やオンライン通話を通して「一緒に食べよう」と声をかけるのもおすすめです。
他には、近所の友人や地域の交流の場に参加してみるのも良いでしょう。



人と会う用事ができることで、時間を意識して生活することにつながるからです
宅配弁当や宅食サービスを活用して食事を固定化する
高齢者が食事の支度や片付けなどを負担と感じているのであれば、宅配弁当や宅食サービスを利用するのもおすすめです。
サービスによっては、毎日決まった時間に宅配弁当を配達してくれるものもあります。
こういったサービスを利用すれば、食事の用意の負担も軽減されますし、毎日の食事の時間も固定化しやすくなります。



近年では、高齢者向けや持病のある方向けの栄養食メニューを配達してくれるサービスも増えています
高齢者におすすめの宅配弁当や宅食サービスは、本記事の後半で詳しく解説します。
見守りカメラやリマインダー機能で食事時間を可視化する
子供たちが現役世代で忙しく、親の食事時間を管理するのが難しい場合には、見守りカメラを導入するのもおすすめです。
見守りカメラを導入すれば、食事をしたかの確認もできますし、どんな様子かも気軽に確認できます。
他にも、アプリなどのリマインダー機能を使用して食事の時間を通知するのも良いでしょう。
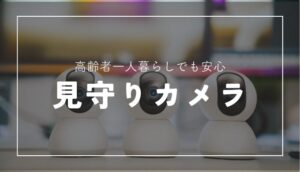
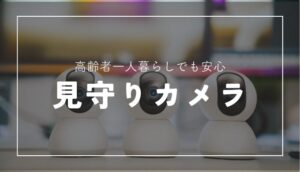
高齢者におすすめの宅食サービス
一人暮らしの高齢者などの中には、料理や片付けなどを負担に感じ、食事を疎かにしているケースも珍しくありません。
そのようなケースでは、単に食事の時間を固定化するのではなく、宅食サービスなどを利用して食生活も同時に整えてしまうのがおすすめです。
宅食サービスには、様々なものがありますが、中でも高齢者世帯におすすめのものは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
ワタミの宅食ダイレクト
- 管理栄養士が設計した栄養バランスのよい冷凍惣菜を食べられる
- 対応エリアは全国各地(一部離島を除く)
- 電子レンジで温めるだけでいつでも好きな時間に食べられる
- 塩分やカロリーに配慮したラインナップで健康管理がしやすい
- 定期購入だけでなく都度注文も可能でライフスタイルに合わせやすい
- まとめ買いで冷凍保存できるため、食事時間が不規則な高齢者でも利用しやすい
ワタミの宅食ダイレクトは冷凍弁当として届くので、自分の好きなタイミングで温めて食べられる点が特徴です。



電子レンジで簡単に温められるので、火を使わなくて良いのもメリットといえるでしょう
惣菜やコンビニ弁当の場合、添加物や栄養の偏りが心配になりますが、ワタミの宅食ダイレクトは管理栄養士監修のため、栄養バランスやカロリーの面でも安心です。



惣菜の種類は100種類以上なので、毎日違うものを食べたい方や同じメニューばかりでは飽きてしまう方にもおすすめできます
私の母の話になりますが、「食べたいと思って注文しても届くときには別のものが食べたくなる、だから生協とか宅食サービスは自分には合わなかった」と以前話していました。
しかし、ワタミの宅食ダイレクトは惣菜の種類が多いため、一度にまとめて頼んでおき、その日の気分で食べたいものを選ぶことも可能です。



種類が多く、偏食気味で惣菜が苦手な父も自分の好きなものを選んで食べてくれると母が喜んでいました
メディミール
- 管理栄養士と医療チームが監修し、健康面に配慮した冷凍弁当を提供
- カロリー・塩分を控えたい、糖尿病や腎臓病など特殊な制限食に対応
- 電子レンジで温めるだけの簡単調理
- メニューは150種類以上、飽きずに楽しめる豊富なバリエーション
- 無添加・国産食材へのこだわりと、やわらか食・刻み食にも対応
メディミールは、管理栄養士や医療専門チームが監修したメニューで、健康を気遣う高齢者や、特定の病気を持つ方の栄養管理をサポートする宅配サービスです。
食事のカロリーや塩分にも細かく配慮されており、宅食でありながら健康維持に役立てやすいのが大きな特徴です。



糖尿病や高血圧の方向けの制限食って家庭で作ろうとすると、レパートリーが少なくいつも似たものになりやすいですよね……
メディミールは品数150種類以上なので、同じものばかりで飽きてしまうことも、食材が偏ってしまうこともありません。



150種類以上であれば、3食×30日食べても同じ献立にならない計算になりますね
また、メディミールは管理栄養士が監修をしているだけでなく、献立作成や商品開発、調理、栄養相談にいたるまですべての工程を管理栄養士が担当しています。



お客様対応も管理栄養士の方が対応してくれるので、何かあったときに相談もしやすいはずです
高齢になり、高血圧や糖尿病など持病が増えてきた方や、制限食の用意が負担になってきた高齢者におすすめの宅食サービスといえるでしょう。
健康直球便
- 管理栄養士監修で、糖質・カロリー・塩分・たんぱく質などさまざまな制限食に対応
- 主菜1品+副菜3品のセットで満足感が高く、バラエティ豊かなラインナップ
- 冷凍で長期間保存可能
- 噛む力・飲み込む力が弱くなった高齢者向けの「やわらか食」「ムース食」も充実
- 1食500円程度から利用でき、割安でコスパが高い宅食サービス
健康直球便は、管理栄養士が監修した栄養バランスに優れた冷凍弁当を宅配するサービスです。



メディミールと同様に、制限食の種類が豊富であり、高齢の方が利用しやすいメニューが揃っています
具体的には、以下のようなコースの中から選べます。
- 糖質・カロリー調整食
- カロリー・塩分調整食
- 塩分・たんぱく調整食
- 消化にやさしい食
- やわらか食
- ムース食
他の宅食サービスと同様に冷凍弁当として届くので、長期保存が可能であり、食べたいときに電子レンジで気軽に回答可能です。
メニューは、いずれのコースも主菜+副菜の構成となっており、ボリュームだけでなく、味やバリエーションも充実しています。
高齢になり柔らかいものや消化に良いものを食べたいと思っていたが、毎日の調理が負担だしメニューもワンパターンになるとお悩みの方にぴったりです。
また、健康直球便は高齢者向けのメニューに特化した宅食サービスであり、一人暮らしの高齢者だけでなく、子供世帯と同居しているものの制限食や別メニューを食べたい方にも向いています。



健康直球便なら料理の負担を減らせ、楽しく食事を摂れるようになりそうですね
高齢者の食事時間についてよくある質問
最後に、高齢者の食事の時間について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 高齢者の食事時間が早い理由は何ですか?
-
高齢者は若い世代に比べて、食事の時間が早くなる傾向があります。
主な理由としては、加齢に伴う体内時計の変化や消化機能の衰えにより空腹感を感じやすくなることがあげられます。
- 高齢者の食事時間はどれくらいが適切ですか?
-
高齢者に限らず、食事は1日3食をおおよそ同じ時間帯に摂ることが一般的には望ましいとされています。
具体的には、朝は起床後1〜2時間以内、昼は12時前後、夜は18〜19時頃までに食べ終えるのが理想です。
就寝直前の食事は消化に負担をかけ、睡眠の質を下げる恐れがあるため、できるだけ避けるべきです。
- 高齢者の孤食を解決する方法はありますか?
-
高齢者の孤食は食事時間を乱すだけでなく、食欲低下や低栄養、さらにはうつや認知症のリスクを高める要因にもなります。
家族が遠方に住んでいて一緒に食べることが難しい場合には、電話やオンライン通話などをしながら食事をするのもおすすめです。
【まとめ】家族の工夫やサービス利用で規則正しい生活を意識していきましょう
高齢者の食事時間が不規則になる背景には、加齢や生活環境、病気や服薬など様々な要因が関係しています。
加齢なら仕方ないと思ってしまうかもしれませんが、放置すると低栄養やフレイル、持病の悪化など健康リスクを高める恐れがあるため、早めの対処が大切です。
家族や介護者と一緒に食べる機会を作ったり、宅食サービスを利用して時間を固定化したりすることで、毎日の食事時間をある程度固定化するようにしてみましょう。
近年では、高齢者向けの宅食サービスも増えてきており、本記事で特におすすめしたのは以下の3社です。



初回割引などのサービスを行っている場合や定期購入サービスを行っている場合もあるので、気軽に試してみると良いでしょう
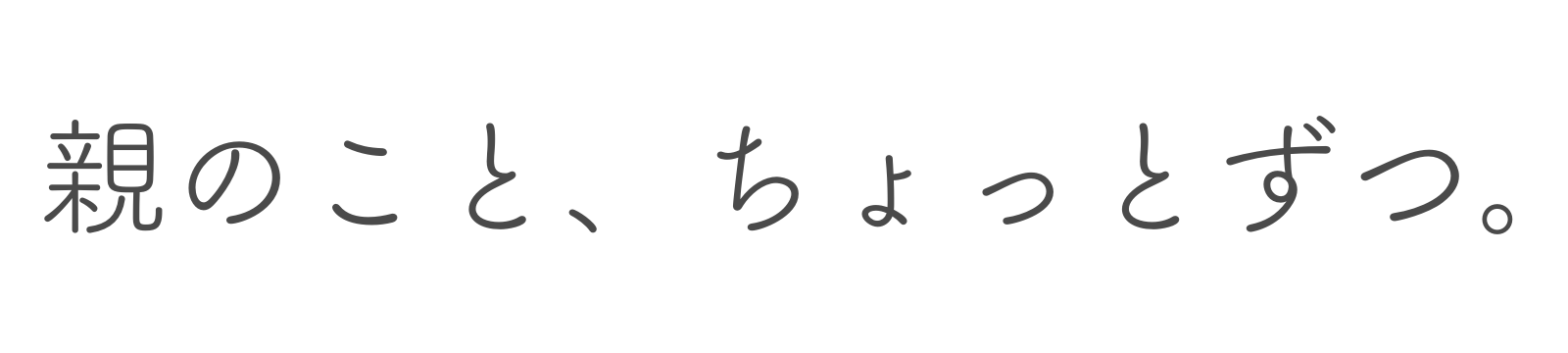

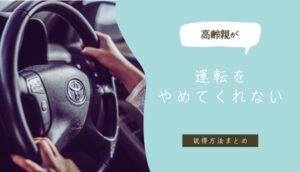

コメント